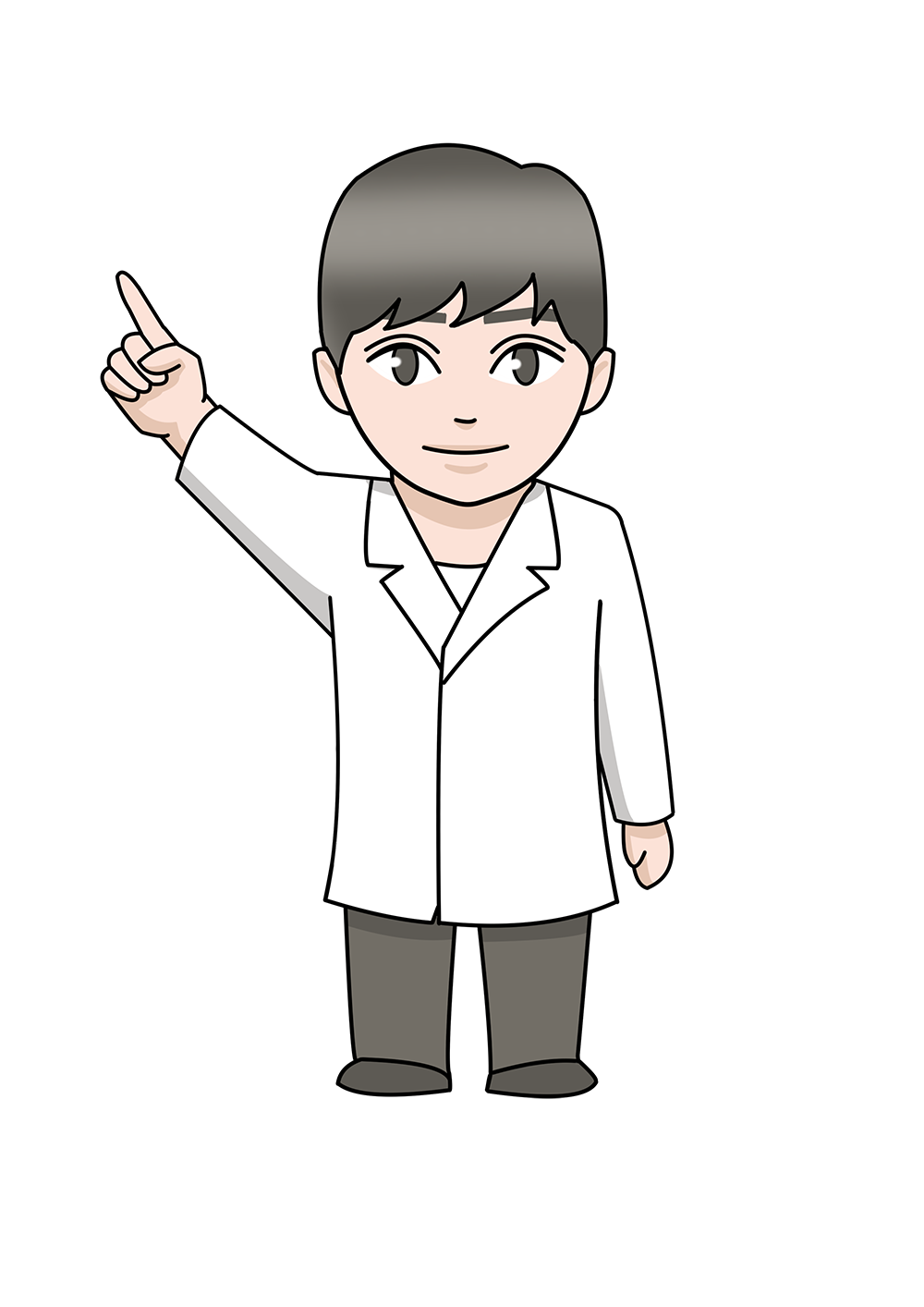

※この記事はリハビリテーションの専門家で、理学療法士である運営者平林と、理学療法士イワモトの考えや意見をまとめて紹介しています。
なので、共感できる部分は共感して、納得できる内容は納得していただけると幸いです。
執筆者・運営者は、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の国家資格を取得しており、実際に病院やクリニック、介護施設など様々な場所で現場で学んできています。
ですので、記事内で紹介している内容は、リハビリテーションの視点を持った国家資格者の視点からみた意見と臨床での事実を述べています。
それを踏まえて、記事の内容は自信を持って提供しています。
しかし、【内容が絶対正しい!】とは思わないでください。
というのも、世の中には、沢山の治療方法や治療の考え方があって。
- どれが正しくて、どれが間違っているのか?
- どれが自分に適している治療なのか?
個人的な意見も沢山あり、個人の解釈や価値観、考え方によって大きく違ってきます。
ですので、『絶対にコレが正しい治療方法だ!!』みたいな考え方はできなくて。
間違いなく言える事は、どんな治療においても、【実際に試してみないとわからないよ】。という事です。
【100%これが正しい】という治療方法は存在しません。
ですので、ここで紹介している内容も一人の理学療法士の意見である事を踏まえていただきたいと思います。
そして、この記事があなたの役に立てばうれしく思います。
1 なぜ手術後に歩けなくなるの?
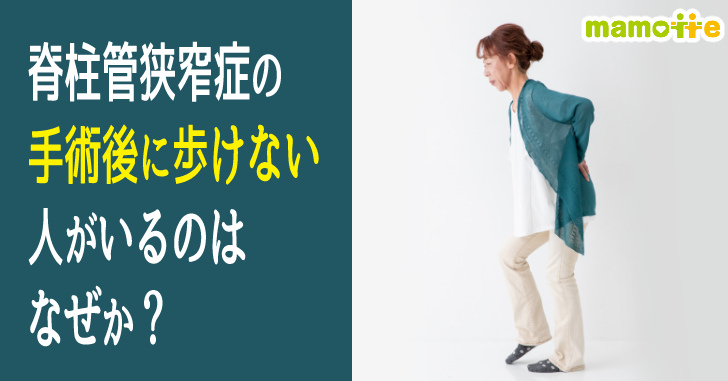
手術後に歩けない状態になってしまう可能性として、大まかに3つあります。
理由① 手術前からすでに歩行困難を生じていた。術後も症状が改善せず、歩行困難が続いている
理由② 手術直後から症状が悪化して、歩行困難になった
理由③ 術後しばらくは良くなったが、そのうちに歩行困難になった
という事が考えられます。
では、それぞれに対して意見を述べていきます。
理由① 手術前からすでに歩行困難を生じていた。術後も症状が改善せず、歩行困難が続いている。
手術前に重度の歩行障害を生じていた場合は、すでに神経が不可逆的変性(永久に回復しない状態)をおこしていることがあります。
神経はある程度の圧迫であれば、神経は回復すると言われています。
しかし、ある一定以上の圧迫が長期に渡って生じていた場合などでは、神経の回復は難しくなります。
このような場合では、手術で神経への圧迫を取り除いても、神経が回復しないため、歩行の状態が改善しないことがあります。
理由② 手術直後から症状が悪化して、歩行困難になった。
手術には避けられないデメリットがあります。
神経への圧迫を取り除く手術を完璧にミスがなくても、神経へのダメージを生じることがあります(例えば、手術に使用する道具で神経を切ってしまうようなことはなくても、触るだけでもダメージを生じてしまうなど)。
これは、手術前には予想できない要素も多くあって、やってみなければわからないという部分でもあります。
このようなデメリットを生じた場合、神経はダメージを受けることとなって、術前よりも麻痺が悪化するなどして、歩行障害を生じることがあります。
手術を受ける場合は、必ずこのようなリスクがある(ゼロではない)ことを理解しておく必要があります。
理由③ 術後しばらくは良かったが、そのうちに歩行困難になった
脊柱菅狭窄症の手術は、1回行えば一生症状が悪化しないというものではありません。
他の部位で同じような狭窄が進行していくこともあります。
しばらく症状が改善していても、そのうちに神経への圧迫が始まれば、また症状が悪化し、歩行障害が生じることもあるのです。
場合によっては、再手術が必要になることがあります。
脊柱菅狭窄症の手術は、神経への圧迫を開放するために、骨の一部を削り取るなどが行われます。
その結果、腰椎の安定性が低下してしまうことがあります。
別の部位の骨まで削ることになると、腰椎が非常に不安定になることもあるので、その場合は、腰椎の不安定性を解消するために、金具(インプラント)を使って、腰椎を固定する手術が必要になる場合もあります。
以上、3つの可能性があります。
2 すごい医者でも、手術の結果は分からないよ
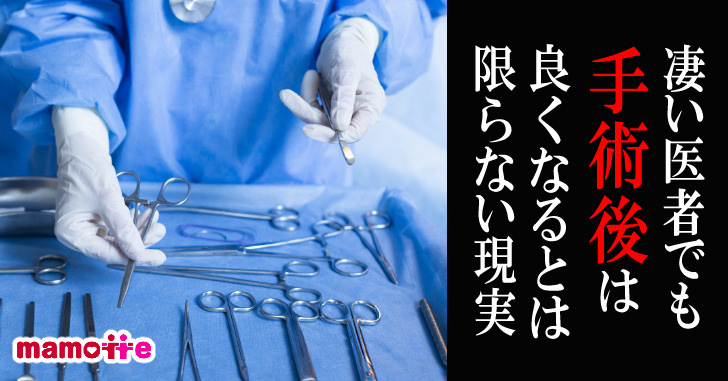
脊椎手術の名医と呼ばれる医師もいます。
そのような医師は、高い専門技術と知識を持っているでしょう。
例えば、内視鏡を使った手術などでは、専門的な研修の終了やある一定以上の経験も必要となります。
高い技術を持った医師は、難しい手術をミスなく行うこともできます。
しかし、それでも脊柱菅狭窄症の症状を100%必ず改善できるわけではありません。
神経へのダメージが大きい場合は、医師の腕をもってしても回復させることができないかもしれません。
手術が上手にできたとしても、脊柱菅狭窄症の術後に残る症状が変わらない。
という可能性はゼロではありません。
どんな名医が行ったとしても、手術を失敗しなかったとしても、症状が改善しない場合もあるのです。
これは、頭の片隅に必ずおいてほしいと思います。
3 手術は本当にやむを得ない時だけにしよう

手術には必ずリスクがあります。
脊柱菅狭窄症は、神経に関わる部分でもあるため、運悪くデメリットの要素が多くなれば、歩行障害が強くなる危険性もあります(多くはありませんが)。
なので、手術による方法は最後の手段と考えて、できるだけリハビリなどの保存療法をしっかりと行うことで対策するのがいいと思っています。
けっして放置せず、できるだけ早期から対策を講じることが大切です。
最後の手段とは言っても、運悪く手術が必要になることもあります。
このような場合、必要以上に先延ばしにすると、術後の回復が悪くなることがあります。必要な場合は素早く決断して、手術を受けるという判断も大切になります。
そのあたりは、医師とも相談して、ベストな時期を選択するようにしましょう。
4 脊柱管狭窄症、予防できるって本当?
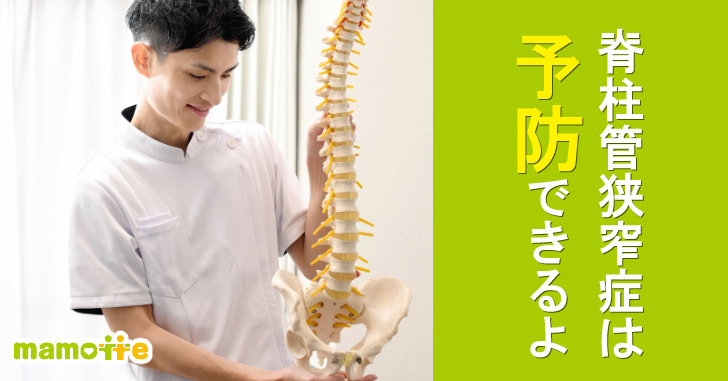
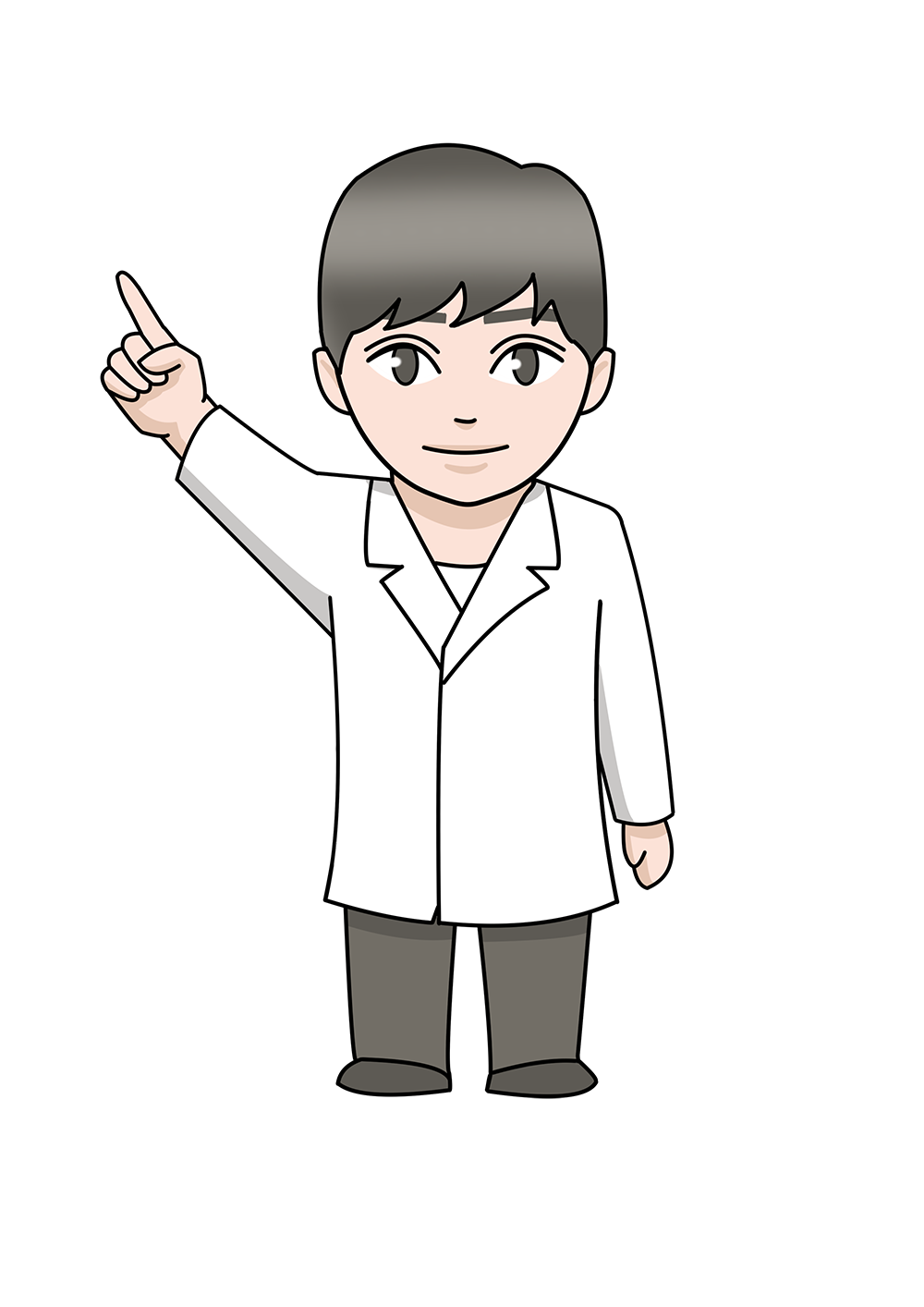
脊髄損傷を聞いたことがあるでしょうか。
これは、事故などで起こることが多いもので、歩く事が難しくなることもあります。
交通事故など、背骨に大きな力がかかるような場合は、脊髄が瞬間的に損傷を起こしてしまいます。
脊柱菅狭窄症は、交通事故のように瞬間的に起こるものではありませんが、時間をかけて脊髄損傷と同じような状態にもなる可能性があります。
しかし、事故と違って、予め予防対策を行うことができます。
完全な予防はできないとしても、腰への負担を下げることで、症状の悪化スピードを減速させたり、手術を避ける取り組みはできます。
手術の技術や安全性は高いですが、それでもまだ、手術のリスクをゼロにすることはできません。
ここで伝えたい事は、脊柱管狭窄症は予防をする事ができるし、手術のリスクをさける事もできる。
という事です。
今から適切な予防の取り組みをして、脊柱管狭窄症の予防をしましょう。
5 まとめ:脊柱管狭窄症の手術リスクを正しく知って、しっかりと考えよう

今回は、脊柱菅狭窄症の術後に歩けない人もいる。というテーマでお話しました。
理由① 術前から歩行障害がある場合
理由② 手術の影響で症状が悪化する場合
理由③ 術後しばらくして再発する場合
上記3つのパターンで術後に歩けない状態になることがあります。
これらは、手術のミスが原因ではなく、避けることのできない理由によって起こるものです。
脊柱菅狭窄症の手術は、最悪の状態を避けるためという意味合いが強く、症状を必ず改善させるものではない事が多いです。(すべてがそうとは限りませんが)
手術を受ける場合は、手術の意味や起こり得る症状についてよく理解しておくことが重要だと思います。
なので、手術は最手段と考えて、できるだけ早めにリハビリなどの対策を行うといいでしょう。
本日も最後までありがとうございました。
執筆:mamotteライター 理学療法士 イワモト
追記・編集:mamotte運営者 理学療法士 平林
【事実です】脊柱管狭窄症の手術後に痛みが残る人もいる!期待はしない方が楽という話
脊柱管狭窄症の手術をしたのに、痛みやしびれなどの症状が残る人がいます。
全ての人がそうではありませんが、少なからず症状が残ってしまう人がいるのです。
なので、手術に対して、期待をしすぎない方が気持ちが楽なのではないか?
というお話をしています。
主観を盛り込んでのお話なので、一つの意見として、参考にしていただけたら幸いです。
手術に不安を持っている人、手術を控えている人に役にたてばうれしいです。

脊柱管狭窄症の手術をして、歩けなくなったという人は少なからずいます。
【手術をしてから歩けなくなった】という解釈をどのようにするのかは難しい部分ではあるのですが。
・手術をしても、実際に良くならなかった。
↓
その結果、良くなったと感じていないので、手術前よりも、歩けなくなったと感じてしまっている。
という場合もあるでしょう。(これは、手術によって改善を期待したが、結果的に良くならなかったので、気持ちのギャップが生じてしまったとも考えられるでしょう)
その中で、手術を必要な人がいるのも事実です。
手術が良い・悪い訳ではなくて、本当に今の自分の症状に手術が必要であるのか?
この事を考えてほしいかなと思います。
その上で、リスクを知って、検討した中で手術の判断をする。
このような考え方をもつといいのではないでしょうか。
参考になれば幸いです。
最新記事 by mamotte (全て見る)
- 体重が引き起こす腰の痛み:肥満が腰痛に及ぼす具体的な影響 - 2024年5月28日
- 腰痛の背後に潜む?専門家が指摘する可能性のある12の病気 - 2022年5月4日
- 腰痛対策!医者に行く前に試すべき生活習慣の見直し方 - 2022年2月17日
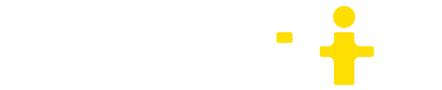













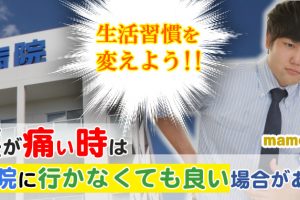




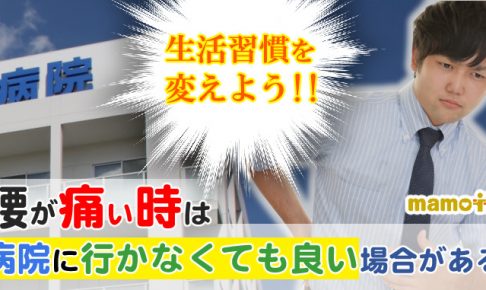



mamotteライターで理学療法士のイワモトです。
脊柱菅狭窄症の手術後に歩けなくなってしまった。
という人も少なからずいます。
「手術したのになぜ?」だろう・・・・と感じてしまう人もいるかもしれません。
今回は脊柱菅狭窄症術後に歩けなくなってしまった原因についてお話します。
この記事を読めば、
◎ 脊柱管狭窄症の手術に対する、適切なリスクを知る事ができます。
『手術をしてはいけない、手術はしない方が良い』という事をおススメしている訳ではありません。
脊柱管狭窄症に手術が必要な方がいるのが事実です。
ただ、その中に手術をしなくても良かった人もいれば、手術をしてしまった後に歩けなくなってしまった・・・。
という人もいるのが実状です。
この事実を知っておく中で、手術をするかしないか?の判断をしていければ良いなぁと思うしだいです。
脊柱管狭窄症の手術を考えている方の参考になれば幸いです。
では、本日もよろしくお願いいたします。