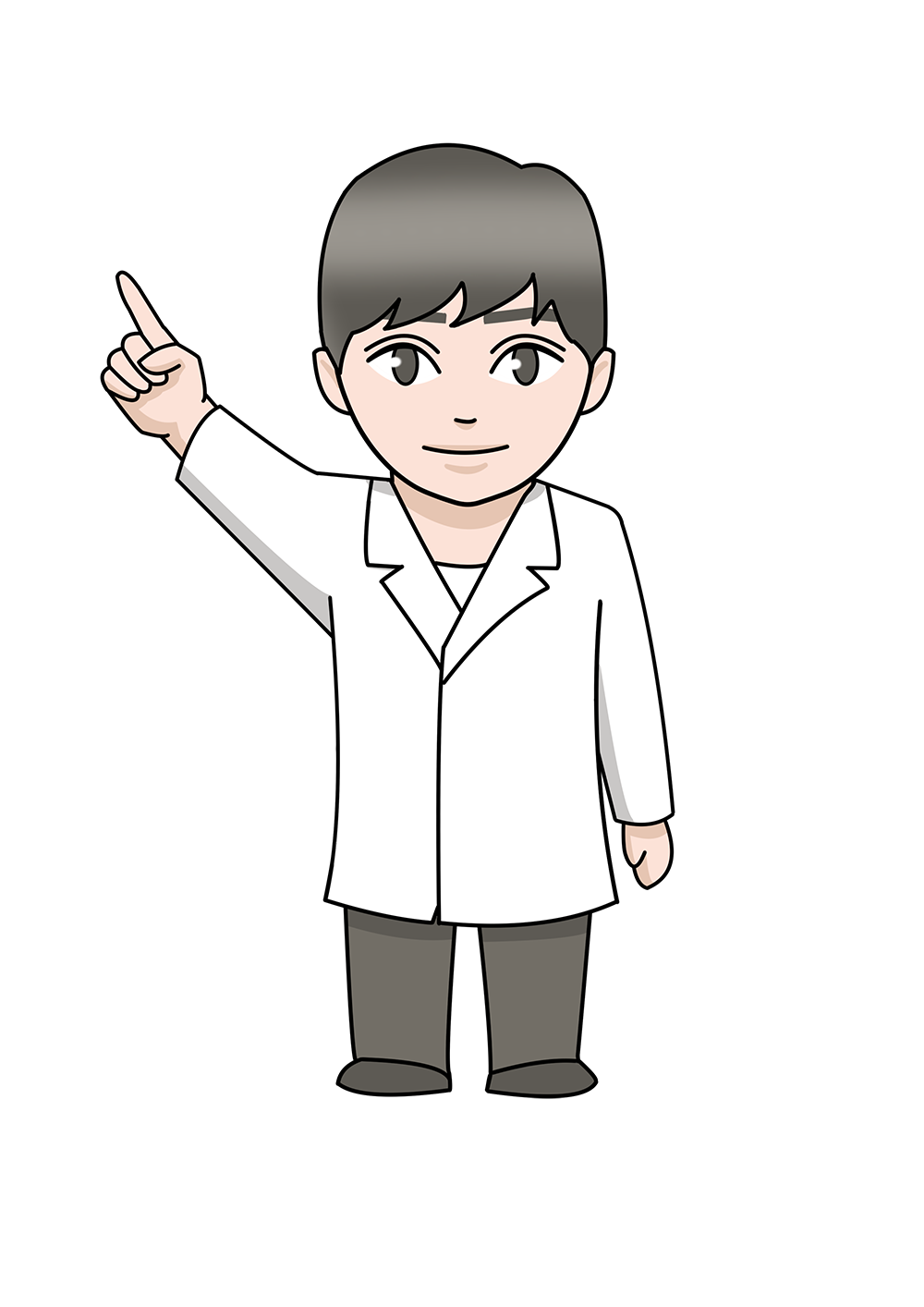
こんにちは。
mamotteライター理学療法士のイワモトです。
「ALS(筋萎縮性側索硬化症)」は、筋力が徐々に弱まるという特徴を持つ疾患です。
一方で、似たような症状を示す「筋ジストロフィー」とは一体何が違うのでしょうか?
この記事では、筋ジストロフィーとALSの主要な違いについて詳しく説明します。
これらの疾患は一見似ているかもしれませんが、症状の詳細にははっきりとした違いがあります。
多くの人が名前は聞いたことがあるかもしれませんが、詳しい内容までは知らないことが多いです。
これらの病気は特定難病に分類されており、今回はこれらの特徴を深く掘り下げて解説します。
この記事を読めば
◎ 筋ジストロフィーとALSの違いを明確に理解し、それを治療に活かすことができます。
といったメリットがあります。
最終的には、筋ジストロフィーとALSについての理解を深め、多くの患者に対する支援が拡大されることを望んでいます。
是非、最後までよんであなたの役に立てば嬉しいです。
では、本日もよろしくお願いいたします。

※この記事はリハビリテーションの専門家で、理学療法士である運営者平林と、理学療法士イワモトの考えや意見をまとめて紹介しています。
なので、共感できる部分は共感して、納得できる内容は納得していただけると幸いです。
執筆者・運営者は、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の国家資格を取得しており、実際に病院やクリニック、介護施設など様々な場所で現場で学んできています。
ですので、記事内で紹介している内容は、リハビリテーションの視点を持った国家資格者の視点からみた意見と臨床での事実を述べています。
それを踏まえて、記事の内容は自信を持って提供しています。
しかし、【内容が絶対正しい!】とは思わないでください。
というのも、世の中には、沢山の治療方法や治療の考え方があって。
- どれが正しくて、どれが間違っているのか?
- どれが自分に適している治療なのか?
個人的な意見も沢山あり、個人の解釈や価値観、考え方によって大きく違ってきます。
ですので、『絶対にコレが正しい治療方法だ!!』みたいな考え方はできなくて。
間違いなく言える事は、どんな治療においても、【実際に試してみないとわからないよ】。という事です。
【100%これが正しい】という治療方法は存在しません。
ですので、ここで紹介している内容も一人の理学療法士の意見である事を踏まえていただきたいと思います。
そして、この記事があなたの役に立てばうれしく思います。
1 筋ジストロフィーとALS:基本的な違いと概要

最初に筋ジストロフィーとALSの違いについて解説します。
その① 筋ジストロフィーの基礎知識
筋ジストロフィーとは、骨格筋や内臓筋などの筋肉が簡単に損傷しやすく、修復も難しいという特性を持つ疾患群です。
この用語は幅広い範囲にわたるもので、単一の病気ではなく、多様な原因によって引き起こされるさまざまな形態があります。
遺伝的要因が大きく影響しており、これまでに50種類以上の関連遺伝子が特定されています。
この病気は主に運動機能に障害を引き起こすものですが、呼吸や心筋機能の障害など、生命に危険を及ぼす深刻な症状が現れることもあります。
特に、心筋や呼吸筋に問題が生じると、患者が完全に寝たきりになることも少なくありません。
筋ジストロフィーは進行性の病気であり、症状の進行を遅らせたり、悪化を防ぐことが医療提供者にとって重要な課題となっています。
また、この病気にはいくつかの異なるタイプが存在し、それぞれに特徴があります。
筋ジストロフィーの主な臨床病型
- ジストロフィン異常症
- 肢帯型
- 先天性
- 顔面肩甲上腕型
- 筋強直型
- エメリー・ドライフス型
- 眼咽頭印筋型
その② ALS(筋萎縮性側索硬化症)の基本情報
ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、手足や呼吸関連の筋肉が徐々に弱くなっていく疾患です。
症状は人によって異なり、手の力が弱くなることから始まる場合もあれば、食べ物の飲み込みが困難になることもあります。
筋ジストロフィーと同じように筋力が低下するのですが、筋ジストロフィーは筋肉自体が破壊されるのに対し、ALSでは筋肉を動かす運動神経が障害される点が異なります。
さらに、ALSでは通常、感覚や内臓機能は障害されません。
原因は完全には解明されていませんが、遺伝的な異常が関与している可能性があり、その解明に向けた研究が行われています。
この病気は進行性で、症状の悪化を防ぎ進行を遅らせることが医療の大きな課題です。
ALSにはいくつかの臨床病型が存在します:
- 上肢型(普通型):主に上肢の筋力が低下し、筋肉が縮小します。
- 球型(進行性球麻痺):主に発声や嚥下に障害が見られます。
- 下肢型(偽多発神経炎型):特に下肢に症状が表れ、腱反射が弱まるなどが特徴です。
その他、呼吸筋の麻痺や体幹筋の障害が起こることがあり、認知症を伴う場合もあります。
2 特定難病についての包括的なガイド
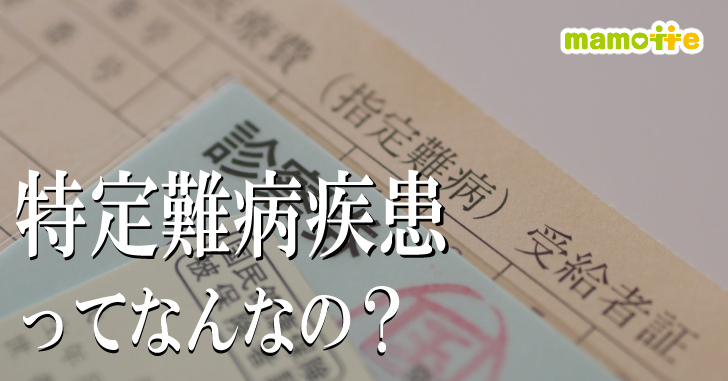
特定難病疾患は、平成27年に施行された法律(難病の患者に対する医療等に関する法律=難病法)によって「指定難病」と呼ばれるようになりました。
疑問① 特定難病とは何か?
2018年4月から、特発性多中心性キャッスルマン病を含む331の疾患が医療費助成の対象として指定されています。全ての疾患を紹介することは難しいですが、以下に代表的なものをいくつか挙げます。
主要な指定難病
- 筋萎縮性側索硬化症
- パーキンソン病
- シャルコー・マリー・トゥース病
- 重症筋無力症
- 多発性硬化症
- 脊髄小脳変性症
- もやもや病
- 悪性関節リウマチ
- 全身性エリテマトーデス
- 再生不良性貧血
- 後縦靭帯骨化症
- 広範脊柱管狭窄症
- クローン病
- 筋ジストロフィー
- 突発性大腿骨頭壊死症
- 強直性脊椎炎
- 先天性側弯症(肋骨異常を伴う)
- 骨形成不全症
指定難病の基準
- 発病メカニズムが未解明であること
- 遺伝子の原因が判明していても病態が不明な場合も含む。
- 根治治療法が確立されていないこと
- 症状進行抑制や対症療法は存在するが、完全な治癒法はない。
- 長期にわたる治療が必要であること
- 症状が基本的に生涯にわたって持続する。
- 患者数が日本国内で一定数未満であること
- 人口の0.1%以下を基準に個別判断する。
これらの疾患には継続的な支援と注意深い管理が必要です。
疑問② 治療の可能性と最新の研究動向について
特定難病(指定疾患)の基準には、「治療方法が未確立であること」と「長期にわたる治療が必要であること」が含まれます。
これは病気が決して治癒しないわけではなく、根本的な治療法がまだ見つかっていないが、症状を管理するための対症療法が存在するという意味です。
したがって、治療が全く不可能というわけではありません。
多くの場合、完治は困難ですが、適切な治療により症状をコントロールすることが可能です。
また、これらの疾患の研究は続けられており、原因の解明に向けて進展しています。
そのため、将来的にはより効果的な治療法が開発されることに期待が寄せられています。
疑問③ 日常生活での対応方法について
現在、難病法に基づき、難病の診断は難病指定医によってのみ行うことが定められています。
そのため、どの病院でも診断や治療が可能なわけではありません。
全国の各都道府県には、難病指定医療機関が設置されており、これらの施設では資格を持った専門医が診断と専門的な治療を提供します。
参考リンク:難病情報センター 指定医一覧
日常生活における重要な注意事項をいくつかご紹介します。
① 転倒防止
歩行時には歩行補助具や装具を使用する、プロテクターを着用する、または必要に応じて車椅子を利用するなどの対策が有効です。
家の中では、段差を解消し、手すりを設置することで安全な環境を整えることが大切です。
② 感染症対策
麻疹、風疹、おたふくかぜ、水疱瘡など、予防接種が可能な感染症には事前にワクチンを接種しておくことが重要です。
また、インフルエンザシーズンには予防接種を受け、感染リスクを減らす工夫をすることが推奨されます。
③ 誤嚥防止
食事中にむせることがあれば、そのまま食べ続けるのではなく、食べ物にとろみを加えたり形状を変更することでむせを防ぎます。
誤嚥は窒息や肺炎のリスクを増大させるため、十分な注意が必要です。とろみ剤は介護用品店や薬局で購入可能です。
3 生活を支える:筋ジストロフィーとALSの対策

では、これより、筋ジストロフィーとALSの患者様にへの考え方についてお伝えします。(これは、個人的な意見も含まれているので、参考として、共感してほしいなと思います。)
対策① 症状の理解と受容
筋ジストロフィー、ALSの病状は人によって違います。
ある人の症状がこうだからといって、自分もそうなるというわけではありません。
症状の出方、進行の仕方も様々です。
多様な病状があることを理解することが先決です。
決してネガティブな例(重症例)のみを探して、悲観的にならないようにして欲しいと思います。
筋ジストロフィーは重症例を除けば、生命の予後は比較的良好な場合も少なくありません。
ALSになったとしても、現代のテクノロジーを活用しながら社会貢献に寄与することも可能です。
著名な物理学者「ホーキング博士」がその代表例です。
病状を正しく理解することで、可能性を高めることができるのです。
対策② 病状進行防止のための日常生活の工夫
簡単に説明すると、筋ジストロフィーは筋肉自体が障害を受ける病気であり、一方でALSは筋肉を動かす運動神経が障害される病気です。
どちらの病気も共通して筋力の低下を引き起こしますが、症状の出方には違いがあります。
それぞれの疾患を正しく理解し、適切な対応を取ることが必要です。
指定難病の場合、専門医による正確な診断と治療が必要であり、難病指定医療機関での専門治療が推奨されます。
日常生活では転倒、感染症、誤嚥に注意し、予防措置をしっかりと取ることが大切です。
楽観的でなくとも、積極的なリハビリテーションを通じて、生活の質を維持し向上させることが可能です。
対策③ リハビリと自己管理の重要性
- 拘縮や変形を予防するために関節可動域訓練を行う
- 転倒の予防(歩行補助具、装具などの使用、車いすの使用)
- 車いす駆動訓練(電動車いすの操作含む)
- 呼吸訓練(肺理学療法)
- 摂食嚥下訓練、福祉用具の活用
- IT訓練(パソコンの操作など)
※筋ジストロフィーでは筋損傷のリスクがあるため、積極的な筋力増強訓練は行わないことが一般的です。
ALSは必要に応じて行っても良いですが、訓練の中心とならないようにする必要があります。
4 まとめ:総括と患者支援への道筋
今回は筋ジストロフィーとALSの違いや対処法などについてお伝えしました。
簡単に言うと、筋ジストロフィーは筋肉自体の障害、ALSは筋肉を動かす運動神経の障害ということができます。
どちらも筋力が低下する点では共通していますが、症状の出方は様々です。
それぞれの病気について正しく理解して、適切に対処する必要があります。
指定難病については指定医による診断、治療が必要ですので、難病指定医療機関で専門的な治療を受けます。
また、転倒や感染、誤嚥に注意するなど、日常生活の中での配慮も大切です。
あまり悲観的にならず、先を見据えたリハビリテーションを行うことで、生活の質を最大限維持することが可能となるでしょう。
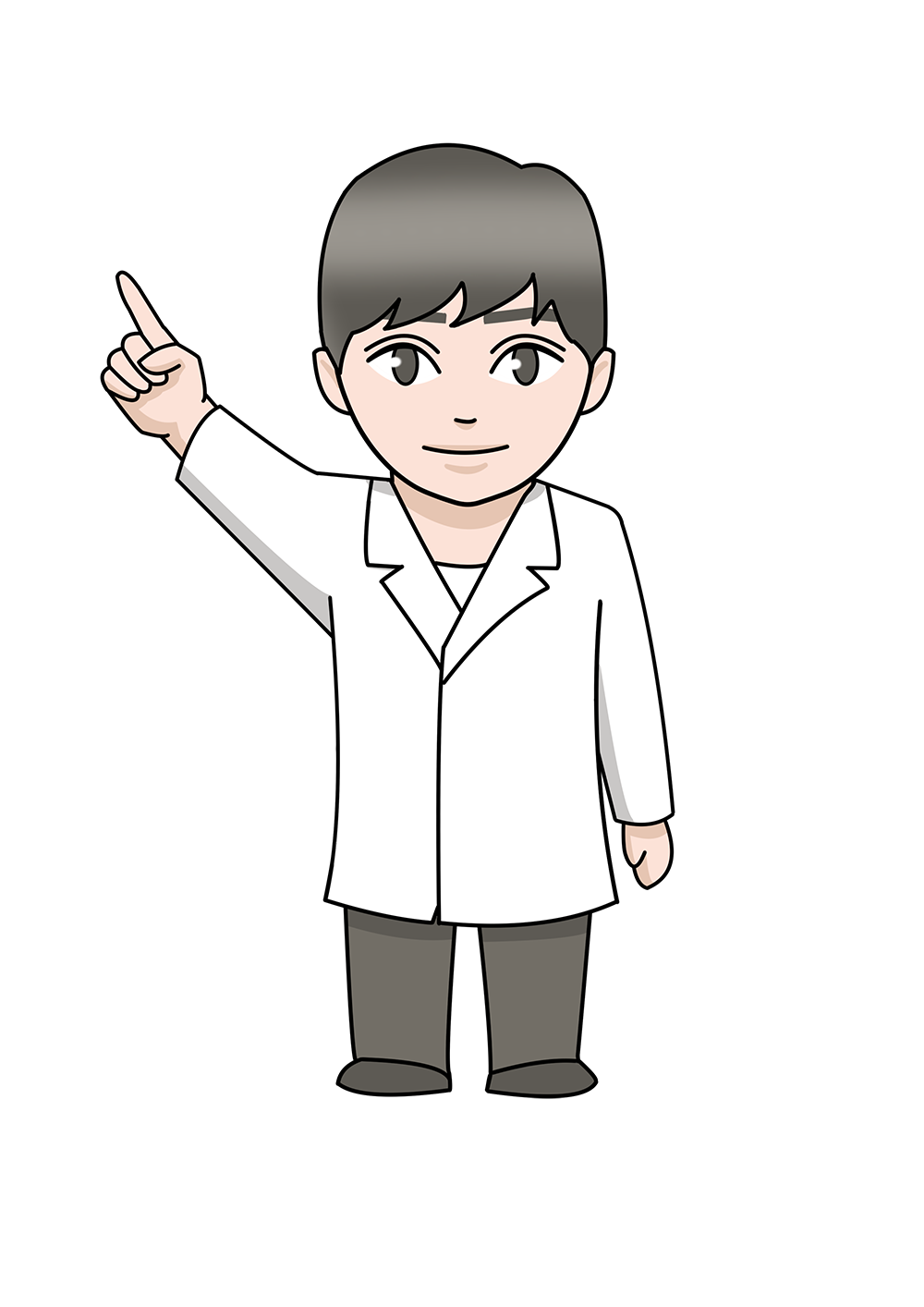
※ 理学療法士イワモトの意見・考え ※
「できるだけネガティブにならず、前向きに…」とお伝えしました。
矛盾するようですが、そんなに簡単にポジティブになんてなれないということは理解しています。
過去に指定疾患を持つ方に接する機会がありました。
その時の私は表面的には笑顔で接しても、心の中では無力感との葛藤であったことを記憶しています(未熟でしたので)。
リハビリは時に残酷な側面を持っています。
毎日筋力増強訓練を行っているのに、どんどん筋力が低下してしまうことがあります。
リハビリを行っているのに、改善しない…すなわち、リハビリでは回復しない病気だということを悟らせてしまうのです。
しかし、現実を知り、絶望を乗り越えて病気を受容し、前向きに生きていく姿に、私は多くのことを教えられました。
その方々は私にとって、貴重な先生という存在です。
病気と闘いながら生きていく姿は周りの者にも勇気と感動を与えます。
「禍福は糾える縄の如し」です。
最後まで読んできただきありがとうございました。皆様のご健康をお祈りいたします
執筆:mamotteライター 理学療法士 イワモト
追記・編集:運営者理学療法士 平林

※ 編集を終えて・最後に ※
実際に、私もALSと筋ジストロフィーの患者さんを担当させて頂いた事があります。
その方は、お二人とも、共通している事がありました。
それは、日々、1日を真剣に生きている。
って事です。
だんだんと自分が弱っていく事を知っていながらも、生活をしている姿をみていました。
40代後半の女性と30代前半の男性でして。
ざっくりな状態は、
- 話はできるが、体は動かず首を動かす事ができるALSの患者さん
- 体に痛みを感じながらも、下肢の装具や杖を使って歩くのができる筋ジストロフィーの患者さん。
の方です。
ホントに毎日が症状との闘いと言っており。
体調が良い日は、問題は少ないのだけど。
体調が悪いと話ができない程辛かったり。
動くのも嫌になるしできない。という状態でした。
こうやって、日々生きる事に頑張っていると思うのです。
なんか、凄いですよね。
五体満足の我々には、100%わかる事ができないのですが。
わかろうとする気持ちは常に持っているつもりです。
このような姿を見ていく中で、我々リハビリを担当する役割としては、
如何に進行を進ませないか?
患者さんの希望やニーズは何なのか?
という事に集中して取り組んで行くべきだと思うのです。
僕は、このように患者さんの気持ちに寄り添えるような療法士になりたいなと思います。
今回の話が少しでも参考になれば嬉しいです。
本日も最後までありがとうございました。
最新記事 by mamotte (全て見る)
- 体重が引き起こす腰の痛み:肥満が腰痛に及ぼす具体的な影響 - 2024年5月28日
- 腰痛の背後に潜む?専門家が指摘する可能性のある12の病気 - 2022年5月4日
- 腰痛対策!医者に行く前に試すべき生活習慣の見直し方 - 2022年2月17日
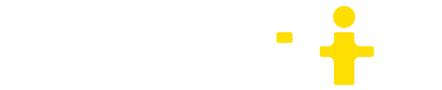

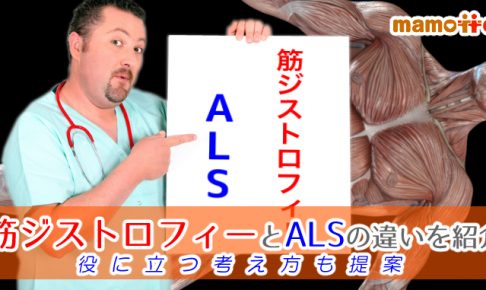












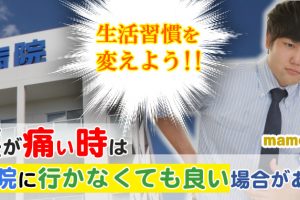




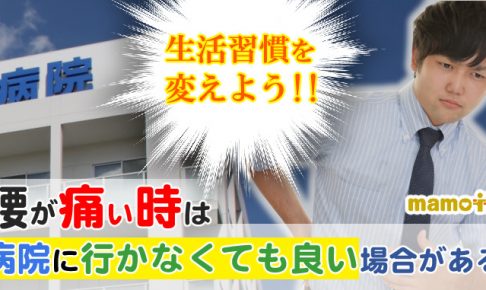



大変勉強になりました、有り難う御座います。患者さんの気持ちになってやつておられることに頭が下がります。また新しい知見がありましたら、ご披露下さい。ご健康をいのります。
宮谷様
コメントありがとうございます。
mamotte運営者で理学療法士の平林です。
ご丁寧にありがとうございます。
少しでも読者様のお力になれたらと想い、ほそぼそと記事を継続させていただいております。
今後も少しでも役に立てるような内容を発信していきたいと思っております。
このようなコメント励みになります。
誠にありがとうございます。
若い頼もしい理学療法士の先生方が、不運にして障害を抱えている患者さんの病状に向き合うた、にさらに研鑽なさってその方々の未来を少しでも切り開いていけるようにお手伝いをなさってください。
徳永秀男 様
コメントありがとうございます。
とても励みになります。
少しでも役にたてばうれしく思います。
この度はコメント大変うれしいです。
ありがとうございました。
mamotte運営者 :平林