

※この記事はリハビリテーションの専門家で、理学療法士である運営者平林と、理学療法士イワモトの考えや意見をまとめて紹介しています。
なので、共感できる部分は共感して頂き、納得できる内容は納得していただけると幸いです。
執筆者・運営者は、理学療法士や作業療法士のリハビリテーションに関する国家資格を取得して、実際の現場で学んできているので、
記事内で紹介している内容は、リハビリテーションの視点を持ったセラピストの視点からみた意見と臨床での事実を述べています。
それを踏まえて、記事の内容は自信を持って提供していますが、【内容が絶対正しい!】とは思わないでください。
というのも、世の中には、沢山の治療方法や治療の考え方があって。
どれが正しくて、どれが間違っているのか?
個人的な意見や見解も沢山あり、個人の解釈や価値観、考え方によって大きく違ってきます。
ですので、『絶対にコレが正しい治療方法だ!!』みたいな考え方はできないと思っています。。
その中で、間違いなく言える事は、どんな治療においても、【実際に試してみないとわからないよ】。という事です。
【100%これが正しい】という治療方法は存在しなくて、個人の解釈によって変わってきます。
ですので、ここで紹介している内容やお話も個人の理学療法士とした意見である事を踏まえていただきたいと思います。
そして、この記事があなたの役に立てばうれしく思います。
1 腰椎分離症でも、スポーツをしても問題ない

スポーツをしている方はここが一番気になるところでしょう。
【腰椎分離症でもスポーツをしても良いのか?】
この点について、話していきたいと思います。
その① 結論:腰椎分離症はスポーツはできるようになる
結論からいいますと。
腰椎分離症でもスポーツはしても良い!
ただし、痛みを感じている場合は、休息は必要。
なので、腰に痛みを感じているまま、無理をしてはダメです。
この点に注意をする必要があります。
最初は我慢できるレベルの痛みであるのが、徐々に我慢できないくらいの痛みになってしまった時に、後になって、改善しない。
酷く悪化して、治りが悪い。
という結果になってしまう可能性が大きいです。
期間的には、1~3か月は様子を見る必要があるかもしれません。
この点は、将来にかかわる大事な事なので、慎重に判断してく必要があります。
是非、意識してほしいなと思います。
その② 腰椎分離症はどうやったら、なるのか?
腰椎分離症は腰椎の骨折です。
腰骨の疲労骨折といって、度重なる骨への強いストレスが積み重なる事によって起こります。
一度の衝撃だけで腰椎分離症になってしまう可能性は少ないと言えます。(もちろん一度の衝撃で骨折が起こることもありますが)。
例えるとしたら、針金を何度も繰り返して曲げ伸ばしをする事で針金が切れてしまう金属疲労に似ています。
なので、腰椎分離症の場合は、腰への負担が積み重なる事で、気づかないうちに疲労骨折していた。
という感じです。
早めに対処できていれば、分離まではいかないでしょう。
なので、腰が痛いと感じた時には、早めに受診して、検査をする方がいいでしょう。
この段階で、単なる腰痛だなぁ・・・と思ってしまうと、腰椎分離の危険性が高くなるかもしれません。
もし、腰椎分離症と診断された場合は、数か月(1~3か月目安)、骨がつながるまでスポーツは控える必要があるかもしれません。
この時に無理やり我慢して動いてしまうと、完全に折れて予後の治りが悪化する事が多いです。
実際にはひびの入った状態で診断を受けることは少なく、完全に折れてしまってから発覚することが多いのが実状です。
腰椎分離症の状態が長くなると骨はつながらないことが多く、分離したままとなってしまいます。
分離したままになってしまうと、腰痛などの症状が強くなければ、スポーツを行うことは辛くなるでしょう。
さらに、神経症状が出ている場合などは、スポーツを辞めなくてはいけない可能性もあるかもしれません。
腰椎分離症から腰椎すべり症という判断に移行する場合もあるし、腰椎分離症と腰椎すべり症の両方を伴わせている感じ。
という人もいます。(必ずなるわけではない)。
ですので、症状が少ない場合でも、将来のことを考えれば腰への負担が大きいハードなスポーツを行っている人は、腰のケアをしながら、上手に対処方法を身に着ける必要があるでしょう。
同じ(ハードな)スポーツを継続する場合は、症状に気をかけて、定期的に診察を受けるのも有効です。
他には、自分で神経症状(下肢への広がるような痛みやしびれ、感覚障害、筋力低下など)が生じていないか、常に気を配っておくのも大切にはなります。
ですので、若いころに腰が痛いと感じたら、すぐに検査をする事が有効かもしれません。
参考になればうれしいです。
2 大人になって、発覚しても気にする必要はない
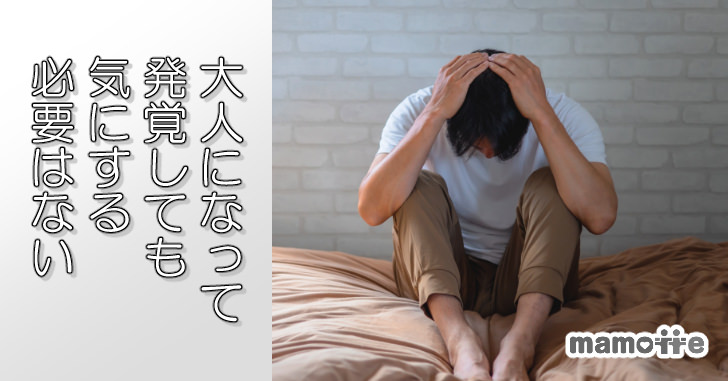
腰椎分離症は、大人になって発覚するケースもあります。
大人になるまで症状がなく、レントゲンを撮った時に分離症が見つかった!!
このような場合は特に気にする必要はないでしょう。
先天的(生まれもって)に腰椎の分離を起こしやすい場合もまれにあるようです。
可能性としては、気づかない間に分離していたことも可能性としてはあります。
症状が出ていなければ、すぐに治療しなければいけないということもないので。
気にしないといけないのは、痛みが強い場合や分離症が起こっている腰椎が移動してすべり症を起こし、その結果神経症状が生じている場合です。
神経症状が出ている場合は、すぐに受診をして、治療に取り組みましょう。
先天的という事で参考までにお伝えしたい点を紹介します。
腰椎は通常5個の椎骨(L1~L5:といった、小さい骨の連なり)が重なっている部分と言われていますが、6個ある場合もあります(10人に1~2人)。
この6個目の椎骨を医療(解剖学)では破格(はかく)などと呼ばれますが、奇形と違って異常ではなく正常の範囲として、捕えられています。
筋肉の数が違っていたり、神経の通る場所が違っていたりと様々な破格があります。
これは、個人差ととらえてよいでしょう。
第6腰椎と腰の障害の因果関係は証明されていないようです。
もともと仙骨になる部分が仙骨に癒合せず第6腰椎として分離しているなどの理由で、そもそも機能的にも大きく変わるものではなく、心配の要素にはならないでしょう。
これは、ちょっとした知識として、捕えて欲しいと思います。
3 腰痛ベルトやコルセットは使用するべきか?

ここでは、腰痛ベルトやコルセットは使用するべきかどうか?
について、述べていきます。
まずは、結論から。
痛みが強い初期は使用した方が良くなりやすい。
(徐々に外していく、コルセットに依存しない様に注意していく必要がある)
これは状態によるのですが、骨がつながる可能性のある場合は、コルセット(硬性)などを使用して腰椎部分を固定することで骨癒合を正常に行えるようにした方が良いです。
骨癒合途中で骨が動きすぎると、偽関節(完全な分離症)へ移行してしまいます。
骨癒合途中でないならば、必ずコルセットやベルトを装着する必要はありません。
しかし、コルセットなどで腰部を固定し、また腹圧を高めることで動作時の腰痛が軽くなるという効果が感じられる場合は使用してもよいでしょう。
試してみる価値はあると思います。
コルセットは治療用装具として保険適用となります。
市販されているスポーツ用のベルト(ザムストなど)は市販専用で医療用ではないため保険適用外となります。
市販でも、医療的なコルセットだとしても、効果はどちらもあるかと思います。
取り組みやすい方法としては、市販のコルセットを購入して、実際に使用して効果を確かめる。
その結果、腰の痛みが軽減したり、楽になるのであればそれでOK
あまり、変わらない、痛いままだ・・・と感じる場合は、医療的なコルセットを採型して作って、試してみるのは効果的かもしれません。
参考としてコルセットを紹介しておきます:一先ず、効果を感じられている方が多いです。![]()
4 腰椎分離症の治療はどんな方法があるのか?

腰椎分離症の治療は、リハビリテーションを行うか、手術をするか?
この2択になるかと思います。
だいたい、どんな治療もリハビリか手術か?
みたいにもなりますが。
これより、もうちょっと詳しく、リハビリテーションと手術について述べていきます。
リハビリテーションが良いのか?、手術をするべきなのか?
理解できるように紹介していきます。
治療法① リハビリテーション(リハビリ)
まず。最初に取り組んでいただきたいのが、リハビリです。
リハビリには、
- 筋力強化
- ストレッチ
- 治療体操
- 日常生活動作の改善
- 姿勢の改善
- 物理療法(温熱、電気など)
など、リハビリと言われる方法はこのような感じです。
筋力強化は、腰を安定化させるために腹筋や背筋を中心に体幹の筋力強化を行います。
この時の筋トレ方法も注意する必要があるので、がむしゃらに行わないようにしましょう。
また、スクワットなども下肢の筋力UPの為には有効です。
筋トレやストレッチだけでなく、リハビリはさまざまな訓練があります。
また、マッサージなどの徒手的療法もよく利用されます(必要に応じてリハビリで実施する場合もあります)。
痛みのある腰部の筋は異常な緊張を起こし、固くなってさらに症状を悪化させる場合があります。
なので、マッサージを行うことで、筋の異常な緊張を改善し、正常な腰椎の動きを促し、痛みの軽減を図る場合もあります。
この時に行うマッサージも、リハビリと解釈する事があります。
ですので、リハビリテーションは幅が広い考え方になる。と思っておくといいでしょう。
治療法② 手術 (固定術)
リハビリを実施しても効果が少なく、痛みが強い場合や坐骨神経の症状が顕著に出現している場合は手術の適応になります。
腰椎の固定術が行われます。
分離した椎骨は不安定で前方に滑るなどして神経症状の原因となりますので、安定性を図るために自家骨移植し、ボルト・金具などで固定します。
状態によりますが、うまく固定できれば1年後(例です)などにボルトを抜くことが可能です。
骨折初期であれば修復術を行い、骨癒合をさせる方法もあります。
5 固定術の後の対応について紹介。(ボルトは抜かなくても良いのか?)
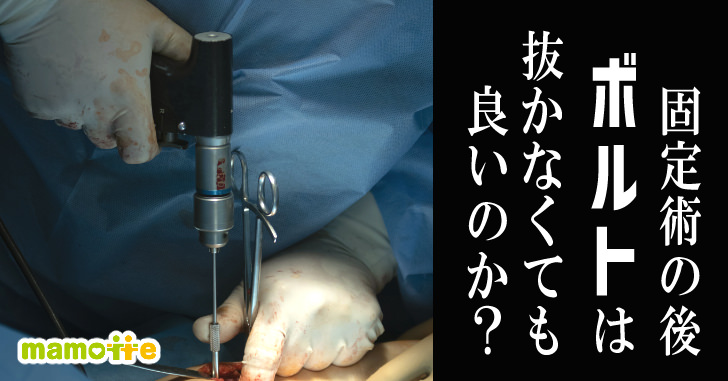
腰椎の安定性、骨の状態、また医師の判断によって違ってきますので、抜く、抜かないを自由に決められるわけではありません。
もしも、希望により抜くことができるという条件がつく手術であれば抜いてもよいでしょう。
基本的にボルトは医療用の、生体と反応しにくい材質(まれに反応する)で作られていますが生体にとっては異物です。
化膿する危険性(低いですが)、可動域の制限や違和感・疼痛の原因にもなる可能性があります。
ボルトを抜くことで痛みや違和感が減少する可能性はあります。
しかし、取り出すためには入院、手術が必要であり、再度切開して取り出すことは、感染の危険があるなどリスクを伴います。
リハビリも必要になるでしょう。
また、金具で補強しておいた方が、腰椎が安定するというメリットもあります。
メリット、デメリット両方ありますので、医師から十分に説明を受けて慎重に判断しましょう。
6 まとめ:腰椎分離症でもスポーツはできるようになる。諦めずにがんばろう
腰椎の分離症は、スポーツなどで腰に大きなストレスがかかることで起きる事がほとんどです。
特に症状が出なければ様子を見ながらの生活で良いと思いますが、しびれや感覚が鈍い、力が入りづらいなどの神経症状が生じた場合はすべり症に移行してしまっている可能性があるので早めに診察を受けて治療を開始しましょう。
適切に管理すればスポーツをすべてあきらめる必要はなくて、腰のケアをしながら注意して、続けていきましょう。
あなたの腰の痛みが改善・軽減の役に立てばうれしいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
執筆:mamotteライター 理学療法士 イワモト
追記・編集:mamotte 運営者 理学療法士 平林

※ 編集を終えて:最後に ※
腰椎分離症と診断されると、不安になるし、どうすればいいの・・・?
とおもいますよね。
- この腰の痛みは治るのか?
- 一生、このままなのか?
- 部活を辞めなくてはいけないのか?
- 体を動かす事ができなくなるのか?
など。
怖くなることばかりでしょう。
確かに、このような可能性があるのですが、全ての人がスポーツができなくなる。
というわけでもありません。
そもそも、分離症でも腰の痛みがなく、スポーツを行える人もいます。
なので、悪化の危険性さえ防ぐことができれば、問題ないと言えます。
その為には、腰椎分離症と診断されても、
- 筋力の強化
- 体の柔軟性の向上
- そのスポーツに適した体の使い方の習得
- 腰椎への負担を軽減させる方法
という対処をしていく必要はあるでしょう。
是非参考にしてください。
最新記事 by mamotte (全て見る)
- 体重が引き起こす腰の痛み:肥満が腰痛に及ぼす具体的な影響 - 2024年5月28日
- 腰痛の背後に潜む?専門家が指摘する可能性のある12の病気 - 2022年5月4日
- 腰痛対策!医者に行く前に試すべき生活習慣の見直し方 - 2022年2月17日
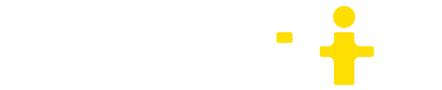








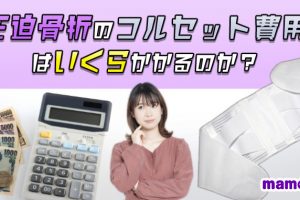


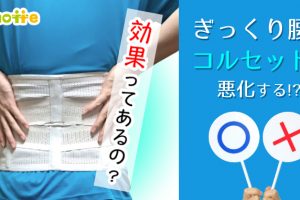


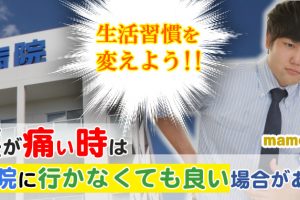



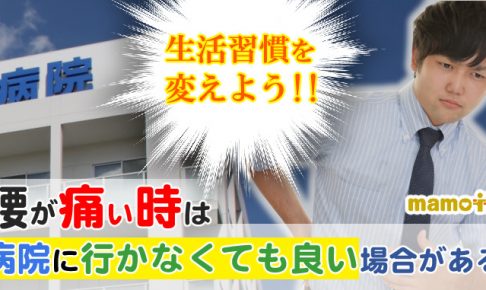



mamotte運営者で理学療法士の平林です。
今回は、「腰椎分離症でもスポーツはして良いのか?」というテーマで記事にします。
腰椎分離症は子供のころからの激しいスポーツやトレーニングによって、起こることの多い骨折の一種です。
また、腰椎分離症は10代に多い症状と言われており、腰の痛みが中心です。
みたいな人も少なからずいるので、どうにかして、良くしないといけません。
この記事を読めば
◎ 腰椎分離症でもスポーツをしても大丈夫、安心してスポーツに取り組めるようになれる方法を知ることができます。
最後まで読んで、参考にしてもらえたら嬉しいです。