
mamotte運営管理者で理学療法士の平林です。
圧迫骨折って聞くと、良くわからないし、治るのかな・・・・・って不安になるのではないでしょうか。
腰が痛くなるし、なんか怖くなりますよね。
そんな中でも圧迫骨折は適切な対処をする事で症状を改善させられる可能性があります。
という事で、今回は圧迫骨折を治す為の適切な対処を紹介します。
この記事を読めば
◎ 圧迫骨折を治すための適切な対処を知れて、腰痛の改善につなげる事ができる
といった点があります。
圧迫骨折で苦しんでいるあなたの力になれたら嬉しいです。
最後まで読んでほしいと思います。

※この記事はリハビリテーションの専門家で、理学療法士である運営者平林と、理学療法士イワモトの考えや意見をまとめて紹介しています。
なので、共感できる部分は共感して、納得できる内容は納得していただけると幸いです。
執筆者・運営者は、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の国家資格を取得しており、実際に病院やクリニック、介護施設など様々な場所で現場で学んできています。
ですので、記事内で紹介している内容は、リハビリテーションの視点を持った国家資格者の視点からみた意見と臨床での事実を述べています。
それを踏まえて、記事の内容は自信を持って提供しています。
しかし、【内容が絶対正しい!】とは思わないでください。
というのも、世の中には、沢山の治療方法や治療の考え方があって。
- どれが正しくて、どれが間違っているのか?
- どれが自分に適している治療なのか?
個人的な意見も沢山あり、個人の解釈や価値観、考え方によって大きく違ってきます。
ですので、『絶対にコレが正しい治療方法だ!!』みたいな考え方はできなくて。
間違いなく言える事は、どんな治療においても、【実際に試してみないとわからないよ】。という事です。
【100%これが正しい】という治療方法は存在しません。
ですので、ここで紹介している内容も一人の理学療法士の意見である事を踏まえていただきたいと思います。
そして、この記事があなたの役に立てばうれしく思います。
1 圧迫骨折を治すための治療方法を5つ紹介

圧迫骨折の治療の多くは手術をしない治療が中心です。
手術をしないで、痛みを軽減させようとする治療方針には
- 【投薬による治療】
- 【コルセットなどの装具療法】
- 【運動療法や物理療法などのリハビリテーション】
などがあります。
この中でも、リハビリテーションが重要だと思っています。
これを踏まえて、これより、圧迫骨折を治していくための5つの治療方法を紹介していきます。
その① リハビリテーションについて
その② コルセットについて
その③ 安静について
その④ 投薬について
その⑤ 姿勢について
是非、参考にしてください。
治療法-その① リハビリテーションをする
リハビリは、筋力トレーニングや可動域訓練などを中心とした運動療法の事をいいます。
圧迫骨折において、腹筋・背筋・下肢筋力の向上や柔軟性維持は重要です。
なので、圧迫骨折を治す為に必要な筋トレやストレッチを行う事が大事になってきます。
また、日常性生活動作や仕事での動作指導や姿勢指導もリハビリに含まれてきます。
というのも、姿勢が悪いと腰への負担が強くなり、腰に痛みが生じてくる可能性が高くなります。
その結果、圧迫骨折であったり、腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症など。
腰痛関連の症状の引き金となってしまう可能性も高くあります。
なので、リハビリテーションは実践する必要がある。
とお伝えしたいと思います。
治療法-その② コルセットをするのもあり
腰痛は、基本的にコルセットを使って余計な動きを抑える事が行われます。
痛みが強いと背中や腰の動きを固定する為に、コルセットを処方する場合が多いです。
コルセットの効果は人それぞれです。
- コルセットをする方が楽になる人もいれば、悪化する人もいる
- 痛みは変わらないけど安心するから着けている人もいる
- お医者さんに言われたから、着けている人もいる
このように感じ方はそれぞれです。
そのなかで、コルセットの有効性については、良い・悪いがあるので、どちらとも言えない。
というのが結論です。
参考にこちらの記事もよろしくお願いします。
しかし、個人的には極力外すように意識する方がいいと思います。
というのも、後に説明しますが、コルセットに依存しすぎてしまってコルセットを外す事ができなくなってしまう可能性があるからです。
また、コルセットをどれくらい着けている方が良いのか?
というのも人それぞれの期間があって、決まっていません。
なので、コルセットをしないと動けない!!!
と思うのであれば、使用しましょう。
コルセットを外すタイミングの目安としては、【我慢できるくらいの痛みになった時】です。
というのも、長期間、コルセットを着用していると体幹の筋力や腰の可動性が低下する恐れがあります。
腹筋や背筋の力が弱くなって、良い姿勢を取りづらくなってしまう可能性があるのです。
さらに、【コルセットに依存したくなる】気持ちも高まります。
長期間のコルセットの使用は避ける方向性がいいでしょう。
圧迫骨折は、自然に修復されるまで2~3か月程かかると言われています。
なので、痛みを感じてから2~3か月経過しつつ痛みが軽減してきたら、様子をみてコルセットは外していく方がいいでしょう。
コルセットに依存しないようにする!!
この思考は大切だと思う次第です。
治療法-その③ 安静しよう、安静するのもあり
圧迫骨折は、身動きが難しくなるほどの痛みが2~4週間は続くことがあります。(全員が動けなくなる。というわけではありませんが・・・。)
安静にしていれば痛みは少ないものです。
圧迫骨折は痛みを感じてから2~4週の間が一番大事な時期とされています。
この期間は無理をせずに、基本的に安静を意識して動ける範囲で動くことも一つの方法とも言えます。
ただ、これも個人によって変わってきます。
完全に安静にしていた方が良い人もいれば、少し動いていた方が良いという人もいます。
なので、安静が100%良い。
みたいに断定できないのが難しいところです。
発症してから1か月の間は、骨折した部分は、変形を起こしやすいので注意が必要になります。
その中で、安静にしすぎても、筋力や関節可動域の低下、体力の低下などが生じてしまう恐れもあります。
なので、安静のしすぎも良くないし、動きすぎも良くありません。
このように言ってしまうと、どうすればいいの?って感じですが。
結論:0~4週間初期は、安静を中心に考えつつ、動ける範囲で動く!!
これが理想的な感じではないでしょうか。
つまり、無理をしない程度で動く。
という感じです。
当たり前といえば、当たり前なのですが、これ以外になくて。
無理をしないで適度に動く!
このくらいの感覚でいる方が、圧迫骨折の痛みが軽減・改善していく人が多い印象です。
参考にしてほしいと思います。
治療法-その④ 投薬をしてみる
圧迫骨折を発症した高齢者の多くは骨粗鬆症の場合が多いため、骨を強くする。
といった考え方もあります。
それが注射や骨形成促進薬などの内服による骨粗鬆症の治療です。
なので、投薬や注射などに頼ってみるのも一つの方法とは言えます。
ただし、投薬も注射も依存はダメです。
骨を強くしている注射と薬を飲んでいるから大丈夫!!
みたいな事は一切ありません。
それ以外の治療方法と併用する事で投薬の効果もグーーーンと上がります。
頼りすぎないようにしましょう。
治療法-その⑤ 日常の生活習慣の改善・指導(悪い姿勢になりすぎないこと)
ここで言うのは、姿勢に関してです。
つまり、良い姿勢を意識しましょう。という事です。
痛みが収まってきて、再発しないためにも、良い姿勢を意識できるようになる事が非常に大切です。
圧迫骨折の一番の原因は、日常的に悪い姿勢になっている事がいえます。
悪い姿勢は背骨を圧迫してしまって、次第に骨をつぶしてしまいます。
これが長時間つづいてしまう事で圧迫骨折になってしまう事がいえます。
なので、良い姿勢を意識する事が重要です。
下記に座った時と立っている時の正しい姿勢をイラストにしました。
参考にしてください。
- 立った時の姿勢
- 座っている時の姿勢
結論:①~⑤をすべて意識できると良い
結局は良い姿勢を意識する。
そして、リハビリによって筋力低下を防いだり、関節可動域の向上を行う。
などの運動療法をしていく事が何よりも効果的です。
圧迫骨折は、日常的な悪い姿勢が大きな原因です。
なので、良い姿勢を意識する事は、効果が高いと言えます。
伴わせて、リハビリによって筋力強化や関節可動域の向上や日常生活動作の指導をすることで、腰への負担を減らして圧迫骨折リスクを軽減させる。
この方法が最も良いと言えるでしょう。
2 圧迫骨折のリハビリの流れ(経過過程)

圧迫骨折を発症してからの経過は大きく分けると、3期間に分けられます。
- 骨折後1~2週間の「安静期」
- 2~4週間の「改善期」
- 5週間以降~の「維持期・再発予防時期」
の3つです。
この経過に沿って治療をすすめる事で、スムーズに痛みを緩和させることができる一般的な指標があります。
ここではそれを紹介したいと思います。
それぞれの時期の特徴や注意点について説明していきます。
経過過程① 安静期(骨折後1~2週間)
圧迫骨折の発症から間もない「安静期」のリハビリには、激しい痛みを伴う場合が多いため注意が必要です。
また、骨がくっつくことを妨げないように、背部への強い負荷や刺激は避けるようにしましょう。
基本的には安静にして、痛みの状態を見ながら可能な範囲で離床していきます。
つまり、初期は無理をしないで、安静が中心です。
その中で、ちょっと動けるならちょっと動く。
ゆっくり歩くなど。軽い感じの日常的な動作はOKです。
経過過程② 改善期(2~4週間)
「改善期」には、痛みはある程度落ち着いている時期ですが、骨が完全にくっついているわけではないので、リハビリは慎重に行います。
安静期よりは身体も動かせるようになっている時期でもあり、運動療法なども積極的に取り入れましょう。
動ける範囲で動く事がポイントです。
ここでは、痛みが落ち着いてきて、動くことがそれほど辛くない時期です。
ちょっと腰が痛いかな?みたいな程度です。
なので、この時期に筋トレやストレッチなどを無理しない範囲で行い、基礎的な筋力の回復、維持・向上などを目指します。
経過過程③ 維持期・再発予防時期(5週間以降~)
この時はほとんで痛みがないか、痛みがあっても、日常生活に支障は少ない時期です。
自宅復帰もできている人が多いです。
この時期は注意して頂きたい5つのポイントがあるので、それを紹介します。
過度な安静は筋力を低下させたり、関節が動きづらくなったりします。
さらに、呼吸機能や心機能の低下を招いたりと、廃用症候群という現象になってしまう可能性もあります。
廃用症候群を起こさないためにも過度な安静は避けなければなりません。
※ 廃用症候群とは、過度に安静にすることや、活動力が低下したことによって、身体に様々な症状が生じる状態をさします。
医療現場で「離床」と呼ばれるのが身体を起こしたり、ベッドから起き上がることをいいます。
離床することで呼吸器系や循環器系の働きを促す事が目的です。
身体を起こす際には痛みを伴いますが、それでも身体を起こして循環器系の働きを促す事が重要になります。
そして、姿勢を維持するための筋肉を鍛えることも必要です。
ベッドの上でも、軽く足をあげたり、足首をバタバタさせたり、手をあげたりして、患部に負担をかけない運動をしましょう。
特に高齢者は姿勢が崩れると、崩れた姿勢によって脊椎が圧迫されてしまいます。
その結果、気がつかないうちに圧迫骨折を発症したりしまうので注意が必要になります。
圧迫骨折初期は身体を前屈させたり、お辞儀をしたりひねったりという動作は痛みを伴うため避けましょう。
痛みが落ち着いてきたりしたら、軽いお辞儀やひねったりする事も可能になります。
痛みの経過と共に判断していく事がいいでしょう。
痛みを軽減するための方法は、低周波療法・温熱療法・マッサージ・運動療法など沢山あります。
一番良い考え方として、『まず、試してみる』のがいいでしょう。
低周波やマッサージなど、一先ず試してみて、楽になったり、気持ち良かったりと感じれば、それを継続すればいいと思います。
安静といっても全く動かないとうわけではなく、痛みの程度に応じて動くことが大事です。
痛みがなく患部に負担のかからない方法を理学療法士に教わって自主トレすることもいいでしょう。
以上、5つのポイント頭に入れていただけたらと思います。
3 圧迫骨折とは何か?ここで一旦、概要について説明する

圧迫骨折とは、背骨が圧迫され潰れてしまう状態であり、高齢者に多い症状です。
酷い場合だと、寝たきりになってしまう可能性もある病状です。
人間の身体は背骨で支えられてて、立つ時も歩く時も背骨に支えられて動いています。
ですが、骨が弱くなってきたり、姿勢が悪くなってくると脊椎である背骨が圧迫されるように潰れてしまうのです。
この背骨が潰れてしまっている状態を【圧迫骨折・あっぱくこっせつ】といいます。
圧迫骨折は「骨折」という病名ですが、骨が折れるわけではなく、椎体が潰れている状態になります。

※圧迫骨折のイラスト※
概要① まずは脊椎について知ろう
脊椎とは一般的には「背骨」といわれている部分で、椎骨(ついこつ)と呼ばれる骨が連結しています。
頭の方から頸椎7個(けいつい)、胸椎12個(きょうつい)、腰椎5個(ようつい)、その下に、仙椎(せんつい)と尾骨があります。
骨同士は関節で繋がり、その間には衝撃を和らげるためのクッションの役目をする椎間板があります。
横から見ると頸椎と腰椎は前弯し、胸椎と仙椎は後弯していて、これを生理的湾曲、S字のように見えることからS字カーブとも呼ばれています。
脊椎は上半身を前後左右に曲げる、伸ばす、ひねるなどの動作をし、立ったり座ったりする動作の時は身体の重さを支えています。
また、歩いている時は身体の上下運動によって受ける衝撃から、脳を守る働きがあります。

※脊椎の理想的な湾曲:イラスト※
概要② 圧迫骨折の病態について
圧迫骨折は、胸の骨の11~12番目から腰の骨の1番目辺りの胸椎と腰椎の移行部で多発するとされています。
しかし、それ以外の部分、胸椎や腰椎であればどの部分でも発症する可能性があります。
そのため、圧迫骨折が発症した部位によって呼び名が変わります。
- 腰椎で圧迫骨折を起こした場合は「腰椎圧迫骨折」ようついあっぱくこっせつ
- 胸椎で圧迫骨折を起こした場合は「胸椎圧迫骨折」きょうついあっぱくこっせつ
と呼ばれています。
概要③ 圧迫骨折はどうやって起こるのか?
圧迫骨折は、日常的に悪い姿勢が習慣されてしまっている事によって生じている事が多い状態です。
また、強い衝撃が加わる事故や尻もち、転倒などでも発症します。
中には骨がもろくなって自然に骨折している場合もありますが、お辞儀や立ち上がろうとした時、くしゃみなどの日常生活の上での単純な動作だけで発症することもあるのです。
なので、本人がいつ圧迫骨折を発症したのか自覚できないケースも多々あります。
以上、概要①~③を参考にしてほしいと思います。
4 圧迫骨折の原因を紹介する

圧迫骨折の一番の原因として、『猫背』のような悪い姿勢です。
猫背は前から気になるけど、どうしても治せないという方も多いです。
ほとんどの人が猫背になります。
この猫背(悪い姿勢)さえ改善する意識さえあれば、圧迫骨折の可能性を少なくできるのです。
さらに、適切な対策と治療や予防を知っていれば、圧迫骨折の痛みを軽減、改善、予防もできます。
これらを踏まえてこれより話していきます。
圧迫骨折の原因としては、
- スポーツ事故や交通事故などの外傷
- 悪性腫瘍の転移
- 骨軟化症などの骨疾患による病的症状
- 猫背など日常的な悪い姿勢
があります。
一番多い原因は骨粗鬆症(こつそしょうしょ)と悪い姿勢が圧倒的に原因として多いです。
骨粗鬆症は高齢者に多く、骨密度が下がって骨折を起こしやすい状態になる事です。
骨がスカスカの状態だと、ちょっとした転倒や動作でも衝撃に耐えられずに脊椎が潰れてしまいます。
これが一つの原因です。
そして、悪い姿勢による腰への負担が一番の積み重なりの原因として考えられます。
日常的に悪い姿勢が癖になっていると、背骨を圧迫している形になります。
この状態が毎日積み重なりきづいた時には背骨が潰れてしまっていた。
という事が一つの大きな原因として考えられています。
なので、悪い姿勢は気づかないうちに圧迫骨折の原因を作ってしまっている。
と言っても過言ではありません。
悪い姿勢を意識して治して、良い姿勢の意識を持つようにするのがいいでしょう。
5 圧迫骨折はどんな症状があるか?

圧迫骨折は、寝返りを打つ時や起き上がった時、歩いている時などの日常生活動作中に背中に激しい痛みがあるのが特徴です。
痛みは背中から腰にまで及ぶこともあり、ひどい場合は下肢の痛みがでることもあります。
圧迫骨折によって、腰や足へのしびれは比較的少ないです。(もし、圧迫骨折と診断されて、腰や足にしびれがある場合は、他の症状が併用している可能性もあるでしょう)
圧迫骨折による痛みの期間はそれぞれありますが、3か月~6か月くらいで軽減している方が多いです。
しかし、痛みが一向に変わらない場合は、他の症状が併用・合併している可能性もあるので、様子をみていく必要があると思います。
一方で、痛みを感じない人もいるのが事実です。
このような方に対しては、まず、【良い姿勢を意識する】ことをして頂き、予防に努めて頂けたらなと思います。
そのまま放置してしまうと椎体の潰れは進行してしまうので、他の椎骨にまで負担がかかってしまう恐れがあります。
そのため、早めの診断が必要となるでしょう。
怪しいなと思ったら、病院に行く。
そんな心持が必要です。
6 まとめ:良い姿勢の意識とリハビリをして圧迫骨折の痛みを改善しよう
如何でしょうか?
圧迫骨折のリハビリ経過について理解できましたでしょうか。
脊椎の圧迫骨折は、人によって痛みの強さも骨折の程度も様々です。
圧迫骨折による痛みは短くても1~2週間、骨折が改善するまでは2~3か月かかるとされています。
ここで伝えたい事は、圧迫骨折だからといって、『痛みが治らない』というわけではありません。
圧迫骨折でも、腰や背中の痛みは無くなる可能性も多いにあります!
この事を覚えて頂きたいなと思います。
一度、潰れてしまった背骨(椎体)は元に戻りません。
しかし、潰れてしまった椎体が原因で、痛みが生じているか、どうかというのは、わかりません。
実際に、椎体がつぶれていても腰や背中に痛みを感じていない方もいらっしゃいます。
ですので、圧迫骨折だからといって、『痛みが治らない』と思わないでほしいなと思います。
そして、何よりも、圧迫骨折を予防する為に運動や良い姿勢を意識することが大切になってきます。
是非、意識して頂けたらなと思います。
mamotte運営管理者 理学療法士 平林

圧迫骨折って診断されると怖くなりますよね・・。
でも、一度なってしまったら骨は元に戻る事はありません。
でも、時間が経つにつれて、痛みが無くなったり、軽減する事は多くあります。
なので、圧迫骨折と診断されても【痛みは改善する・軽減する・消失する】。
この事を強く覚えて欲しいかなと思うのです。
実際に圧迫骨折の患者さんを治療しても、痛みが無くなる人も沢山いるわけだから。
私はこのような患者さん実際にみてきたから言える事でもあります。
なので、あなたにも諦めずに治す行動をとり続けてほしいなと思う次第です。
是非、頭の片隅にでもこのような考えを持っていただけたらと思います。
圧迫骨折を治す為の評価の考え方について紹介しています。
その① 昔の圧迫骨折か、直近の圧迫骨折か?
その② 痛みの強さを知る
その③ 自分の姿勢分析をして、悪い姿勢になりすぎていないか確認する
上記の3点について主に述べています。
圧迫骨折の症状軽減・改善に繋がる考え方につながると思います。
是非、読んでやってください。
最新記事 by mamotte (全て見る)
- 体重が引き起こす腰の痛み:肥満が腰痛に及ぼす具体的な影響 - 2024年5月28日
- 腰痛の背後に潜む?専門家が指摘する可能性のある12の病気 - 2022年5月4日
- 腰痛対策!医者に行く前に試すべき生活習慣の見直し方 - 2022年2月17日
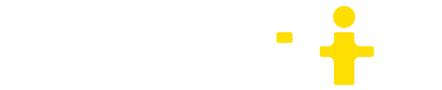
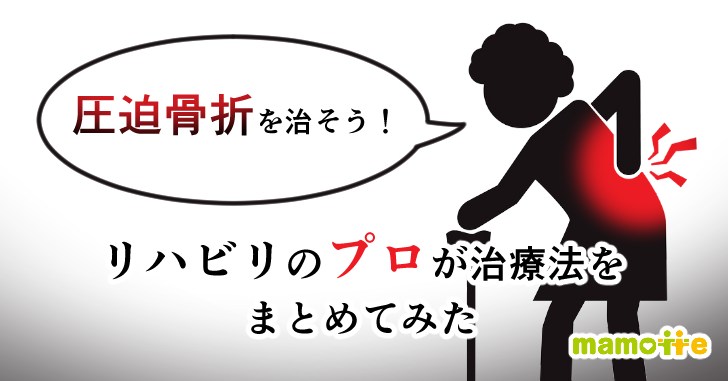


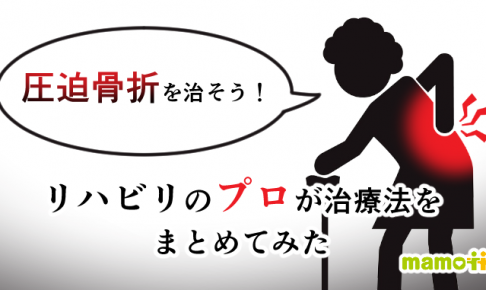







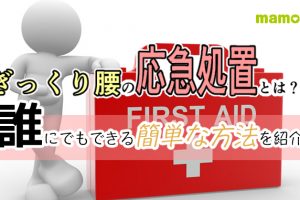



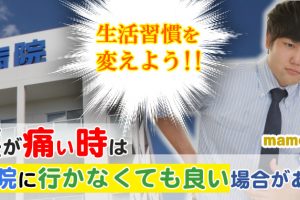




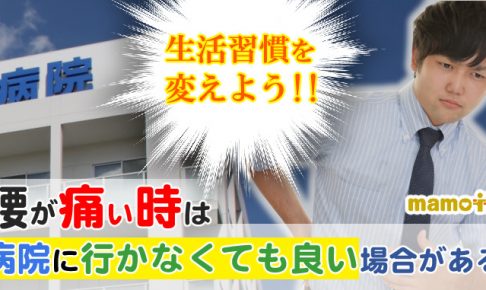



2020年4月初めに腰椎圧迫骨折になりました。当記事によっていろいろな知識を得ることが出来ました。現在は痛み止め薬を服用していますが痛みが大分薄らいできました。車の運転や買い物に行くことが出来るようになりました。腰痛の解消にはまだ時間が掛ると思っています。先日からウォーキングや家の中で階段の上り下り等の運動をしています。
今の悩みは猫背と下腹のポッコリです。どんな対策方法があるかアドバイスいただければ有り難いです。
寺西さん
コメントありがとうございます。
ご状態かしこまりました。
痛み止めにおいて、痛みが落ち着いているのであれば。
一先ず、良いですね。
確かに、痛みが改善するには時間がかかるかもしれません。
しかし、痛み止めで痛みが落ち着いてきているのであれば、比較的早めに良くなるのかなぁ。
と感じております。
ウォーキングや階段昇降も無理のない範囲で行うのは良いと思います。
【動ける範囲で動く】
というのが一番ですので。
で、猫背と下っ腹のポッコリに関してですね。
・猫背に関しては、寺西さんに適した良い姿勢を覚える・身に着ける。
というのが必要かと思います。
正直、ここが一番難しい部分だと思うのですが。
良い姿勢を学ぶ!!
やはり、これだけは専門家に聞くのが一番早いかと思います。
・下っ腹のポッコリについては。
体重に関してでしょうか?
また、下腹部が前に出てしまった悪い姿勢になると、下っ腹がポッコリしてしまう人もいます。
体重が増えてしまうと、良い姿勢を維持するのは少し難しくなりやすいです。
もし、体重が比較的増えている場合はやはり、体重を減らす努力が必要になるかと思います。
その中で、体重を減らすには、体重を増やさない。
という思考も一つありかもしれません。
以上、お答えになっているでしょうか?
よろしくお願いいたします。
記事読ませていただきました。3m位のところから落ちて第一腰椎圧迫骨折でした。2ヵ月半位経ちますが我慢できる痛み、腰が重い感じが続いています。これから痛みが続くのか無くなっていくのか不安です。いいアドバイス頂けるとうれしいです。年齢は50代半ばです。骨の密度は問題ありません。
真様
コメントありがとうございます。
ご状況ありがとうございます。
3mとはだいぶ高いですね・・・・
2か月半くらい経って、痛みと重い感じが続いてると確かに今後が不安になりますよね。
という中で、まず、私の意見からお伝えさせていただきますと。
痛みは軽減・改善方向に持っていく事は可能かと思います。
骨密度は問題なくて50代半ばという事で。
まだまだ、改善の余地は大きくあると思います。
(個々の状況や痛みの経過過程によって、左右する部分も多いので、一概には断定できないのと、
実際に文章上だけですと、細かくお伝えできない点もありますが。)
お伺いしたい事が。
◎2か月半経過する中で、痛みが徐々に軽減してきているのか?
それとも、ある程度まで軽減したけど、それ以上良くなっていかないのか?
どういう感じでしょうか。
例:60%くらいは、改善したけど、これ以上良くなる感じがしていない。
上記はどのような感じでしょうか?
また、痛みや腰が重い感じがする場面はどのような時か?
これを洗い出してみるといいかもしれません。
例えば
・座っていたり、腰を丸めている時などに腰に痛みを感じる、重い感じがする
・歩いている時に痛みを感じている
・逆にこの姿勢だと、痛みも腰の重い感じも感じない
など。
一日を通して、すべての時間帯に痛みや腰の重さを感じているのか?
痛みや腰の重さを感じていない姿勢はどれか?
などを確かめる事によって、腰の痛みを回避する動作や改善の為に必要な行動をみつけだす事ができます。
そうする事で、痛みの改善を目指す事は可能だと思います。
現状では、このようにお伝えするしかできなくて申し訳ありません。
しかし、間違いなく言える事は、
2か月半たっているとしても、今の症状は改善する可能性が高いと思います。
改善の為にやれることもまだまだあるでしょう。
不安になる気持ちも当然だと思います。
しかし、不安になりすぎないで良くて。
改善する方向性だけを見てよいと感じます。
参考になれば幸いです。
お返事がかなり遅くなってしまってすいません。コメントありがとうございます。2~3ヵ月位前に病院を変えて診察してもらったら破裂骨折でした。骨は治癒しかかっているけどまだ駄目です。しびれとか歩きにくいと神経症状はありません。しかし脊髄の方に膨らんでいます。腰の痛みもさほどないけど硬性コルセットして車を運転して買い物、散歩など日常生活はしているものの仕事は体を使う仕事なので怖くて出来ません。これからも保存治療して骨がついていくのか心配です。今は手術という話しはありません。今は骨粗鬆症の注射を適応外使用してます。長くなってしまってすいません。このような状況ですがお返事いただけるとうれしいです。
真様
コメント、お返事ありがとうございます。
破裂骨折との事で、ご状況ありがとうございます。
破裂骨折も圧迫骨折も医師の判断や解釈で変わってくる点もあるので。
圧迫骨折にも近いし、破裂骨折にも近いという、微妙なところなのでしょう・・・。
どちらにせよ。
骨は治癒してきており、現在は神経症状がない。
というのは良い事ですね。
さらに、硬性コルセットで日常生活レベルはできる。
との事ですので、良い傾向なのではないでしょうか。
現在は、コルセットなどで腰を動かないようにしてるので、痛みがさほど感じない。
状態かと思います。
で、主題の
【保存治療して骨がついていくのか心配】との事ですが。
この点に関しては、正直わかりません。
骨がついていく可能性もあるし、完全に骨がくっつかない。
という状態もありえます。
なので、どちらとも言えないのが実際です。
しかし、骨がつかなくても、痛みが改善する可能性はあると思います。
というのも、現在、日常生活レベルの生活ができている事もあるので。
全くダメではないと感じました。
ですので、段階的に治療を踏まえていけば改善していくのではないか?
とも思います。
硬性コルセットの後は、軟性コルセットに代わり。
徐々に体を動かす事ができるようになってから、ストレッチや軽い筋トレなどは必要になってくるでしょう。
この点は、医師の判断とリハビリの進め方によって、大きく変わってくる部分ではありますが。
手術の話がない事からも、保存治療で問題ないという解釈なのでしょう。
私個人的な意見として、手術は最後の最後の手段と考える方が良いと思っています。
まだ、保存治療でできる事が沢山あるので、そちらを優先する方がいいと感じます。
今後のお仕事に関しては、体を使うのがどのくらい使うお仕事なのか?
によって、大きく変わってくる部分もあるかと思いますが。
一先ずは様子をみていくのがいいでしょう。
仕事開始時期をいつにするか?
場合によっては、仕事内容の相談をしていく必要もあるでしょう。
このようなお答えにはなりますが。
現在の状況でしたら、現状維持で保存治療していくことで経過をみていく。
ストレッチや軽い筋トレなど。リハビリをどのように進めていくのか。
現在の担当医と相談していくのが良いと思います。
以上、参考になればうれしいです。
また、なんでもご連絡くださいね。
お返事ありがとうございます。心から感謝します。あなた様の言葉が本当に支えなります。助かります❗️来月CTとレントゲンがあるのでまた担当医と話し合ってみます。ありがとうございます。
真様
とんでもありません。
そのように感じていただけて、幸いです。
ただ、お答えした内容すべてが事実なので。
私、個人的にもそのように思っています。
担当医様と話し合って、治療方針が固まれば良いですね。
応援しております。
運営管理者:理学療法士 平林
平林さん今晩は。いつもコメントありがとうございます。今日診察行ってきました。レントゲンとCTを撮った結果自己注射とコルセットをした効果があって7~から8割ついていると言うことでした。ひとまずは安心しました。硬性コルセットは今日から外してもいいと言う事なので外しましたが腰が痛いです。なにか平林さんからいいアドバイス、リハビリに関する事があればヨロシクお願いいたします❗️夜遅くにコメントしてすいません。
真様
お世話になっております。
コメント、ご連絡ありがとうございます。
7~8割骨がくっついている。
との事で、良かったですね!!
硬性コルセットも外して良いという事は順調なのではないでしょうか。
おそらく、まだ腰の可動域制限(柔軟性の低下)があるので、腰も動かすと痛い時が多いかとは思います。
これから課題になってくる点として。
① 軟性コルセットに依存しすぎない
→コルセットを着ける場合と、着けない場合を分ける。
最終的には、コルセットは使用しないでも腰の痛みをコントロールできるようになる。
これがゴールになるかと思います。
その為には、コルセットの使い方が大事で。
・沢山移動するとき
・体を動かす時、
・腰に負担がかかりそうなとき
などにコルセットは使う。
とコルセットの使用タイミングを検討していく必要はあるかなと思います。
② 腰を中心としたストレッチを行う。
これは、ただのストレッチです。
腰の可動域を改善させるようなストレッチをする必要があると考えます。
以上、簡単にはでございますが、ご参考になれば幸いです。
腰の痛み改善できるといいですね!!!
引き続き、よろしkお願い申し上げます。
mamotte運営者 理学療法士 平林