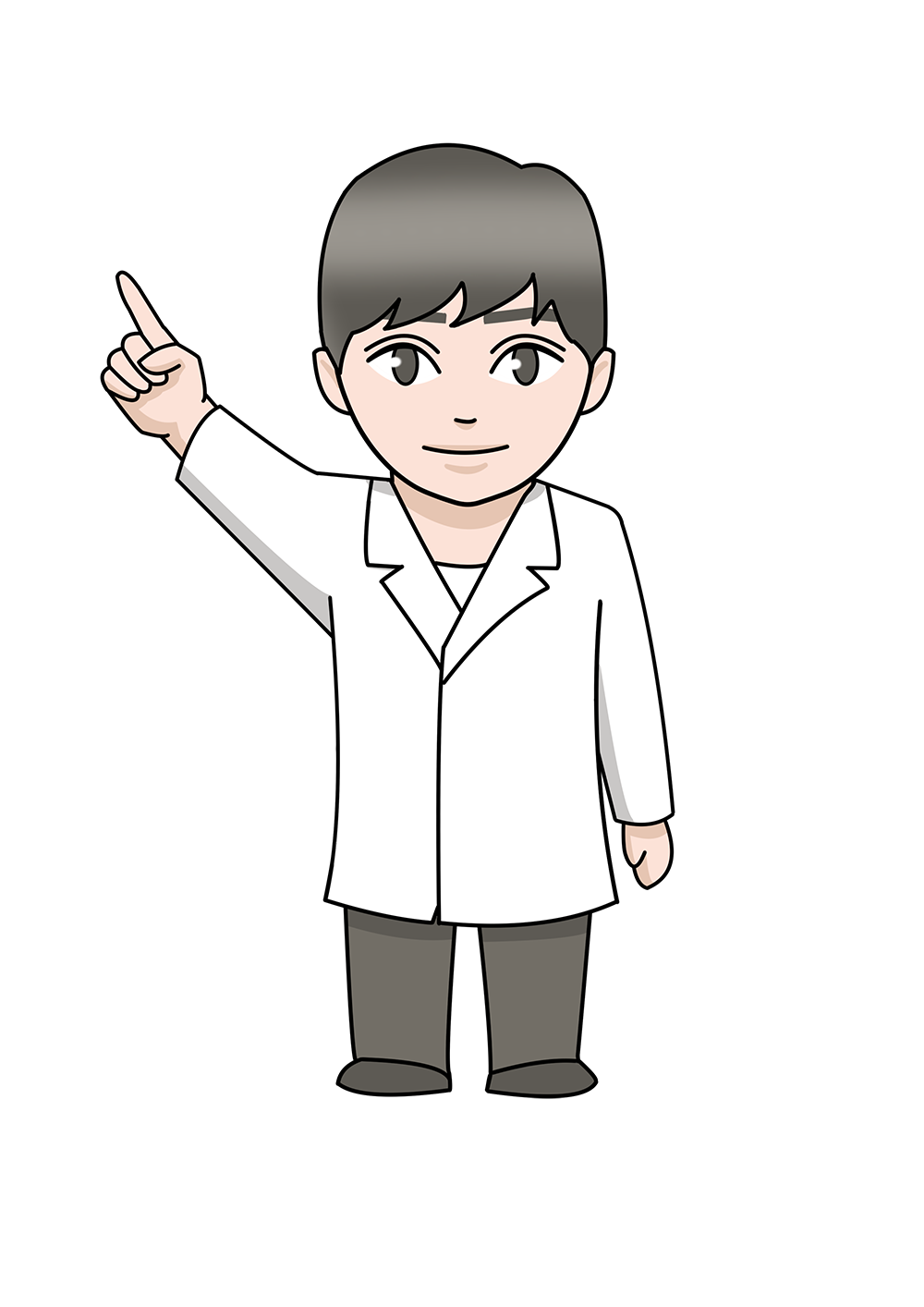

※この記事はリハビリテーションの専門家で、理学療法士である運営者平林と、理学療法士イワモトの考えや意見をまとめて紹介しています。
なので、共感できる部分は共感して、納得できる内容は納得していただけると幸いです。
執筆者・運営者は、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)の国家資格を取得しており、実際に病院やクリニック、介護施設など様々な場所で現場で学んできています。
ですので、記事内で紹介している内容は、リハビリテーションの視点を持った国家資格者の視点からみた意見と臨床での事実を述べています。
それを踏まえて、記事の内容は自信を持って提供しています。
しかし、【内容が絶対正しい!】とは思わないでください。
というのも、世の中には、沢山の治療方法や治療の考え方があって。
- どれが正しくて、どれが間違っているのか?
- どれが自分に適している治療なのか?
個人的な意見も沢山あり、個人の解釈や価値観、考え方によって大きく違ってきます。
ですので、『絶対にコレが正しい治療方法だ!!』みたいな考え方はできなくて。
間違いなく言える事は、どんな治療においても、【実際に試してみないとわからないよ】。という事です。
【100%これが正しい】という治療方法は存在しません。
ですので、ここで紹介している内容も一人の理学療法士の意見である事を踏まえていただきたいと思います。
そして、この記事があなたの役に立てばうれしく思います。
1 坐骨神経痛を治す為に必要な知識

早速ですが、坐骨神経痛を治す為に必要な事を考えてみました。
まず、根本的な治療法は、坐骨神経への圧迫を取り除くことです。
確実に神経への圧迫を取り除くためには、手術を受けるしかない。という意見もありますが、実際には症状が軽い場合や進行していない場合は症状が酷くても手術をしないで治る可能性があります。
なので、手術をしないで済むのであれば、まずは、手術をしない方法で治療をする方がいいのではないでしょうか。
手術は苦痛やリスクを伴うため、現実的には、手術をするのは最終手段がいいと思のです。
治療法は症状によって違ってくるため、一概に『コレが良い』というのは断定できません。
坐骨神経痛になってしまっている原因もそれぞれ違ってくるので。
- 椎間板ヘルニアに近い症状なのか?
- 脊柱管狭窄症い近い症状なのか?
- 腰椎すべり症に近い状態なのか?
といったように、治療方法も若干変わってきます。
ですので、坐骨神経痛でも、どのような診断・症状に近いのか?を知る必要があります。
症状や診断がある程度わかれば、その治療方法に従って治療を進めるのが良いと言えます。
脊柱管狭窄症のように、間欠性跛行のような症状があれば脊柱管狭窄症の治療を行う
腰が純粋に痛いだけであれば、良い姿勢を意識して、腰への負担を減らす努力をする
など。
症状や状態によって、治療方法を変えていく。
といった感じで、坐骨神経痛を治す為に必要な考えは、【現在の症状を知る】そして、症状によって治療法を選択していく事だと思います。
2 坐骨神経痛の予防策!実践的な対策を紹介

次に、坐骨神経痛の対策について話します。
結論としては、【日常的に腰に負担がかかりすぎないように配慮することです】
- 良い姿勢を心がける
- 長時間同じ姿勢にならないようにする(途中で体操するなど)
- 必要に応じてコルセット、クッションなどを利用する
- 日常動作の仕方に注意する(腰への負担を最小にする)
- 体幹筋、下肢の筋力が弱くならないように維持する
- 柔軟性を保つためのストレッチをする
- 運動不足の方は適度な運動を行う(ウォーキング程度)
- 肥満にならないようにする
- 症状が出たら医師の診断を受けて適切な治療を開始する
- 医師の指示に従い腰痛体操などを試してみる
そのほかにもありますが、早期から対策できると良いでしょう。
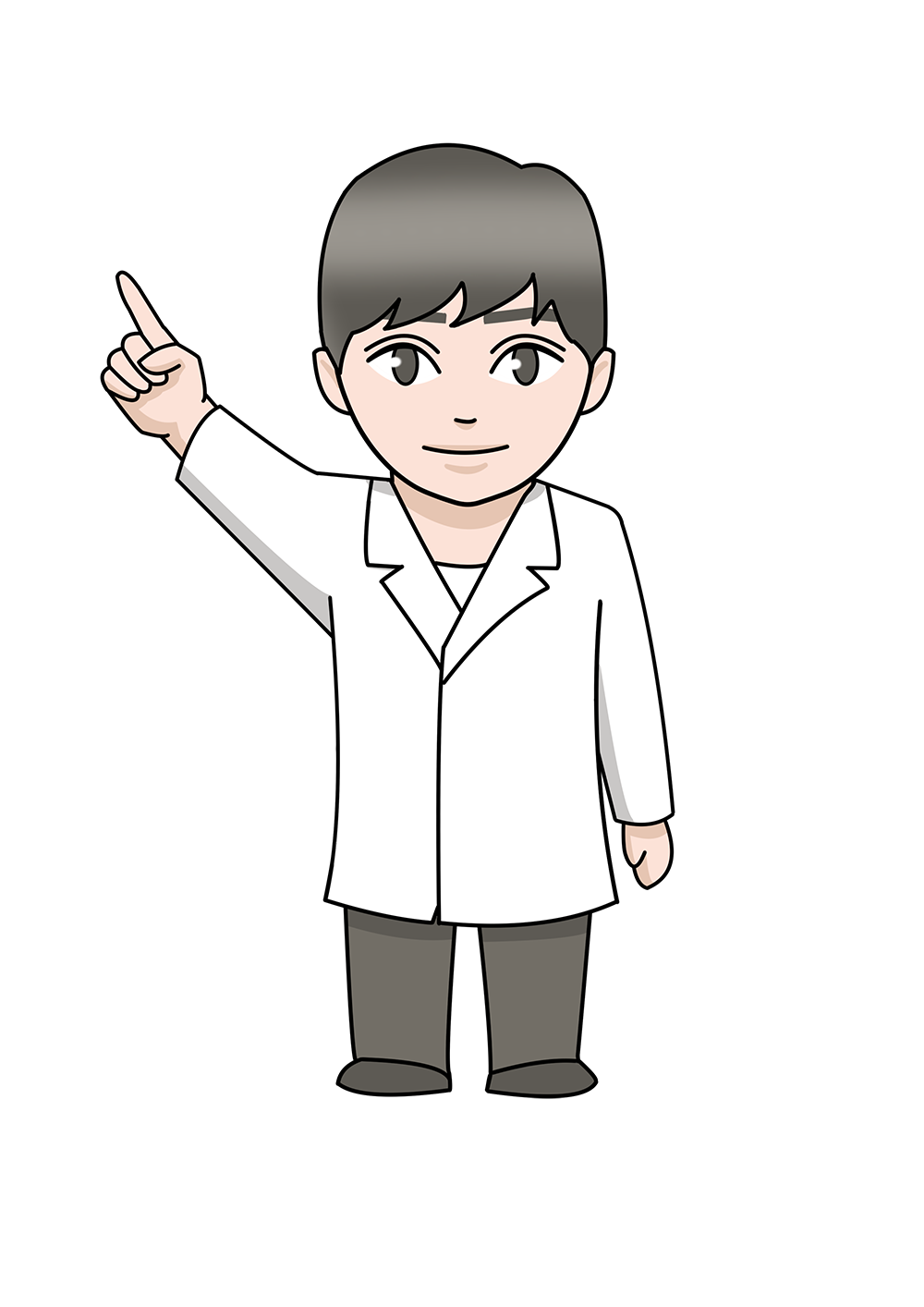
※ 理学療法士イワモトの考え ※
坐骨神経痛はその名の通り痛みを伴う症状ですが、坐骨神経が障害されても痛みを感じない場合もあります。
しびれや感覚障害(感覚が鈍くなる)、筋力低下が主な症状になることもあります。
痛みがないからといって、坐骨神経が問題ないと安心してはいけません。
日ごろから両足の感覚に左右差がないか触ってみたり、つま先の上がり方が左右同じかを確認して、異常を早期に発見するよう努めましょう。
医師にとっては、診断を短時間で行うために情報が非常に重要です。
痛みの出る場所、感覚が鈍い場所、筋力が弱い場所、症状がいつから始まったか、どんな時に症状が出るかなどの情報をまとめて正確に伝えることが、早く正確な診断につながります。
私自身の経験ですが、医師に症状を正確に伝えなかったために、坐骨神経障害を見逃されたことがありました。
このようなことが起こらないよう、情報はしっかりと伝えましょう。
「こんな情報が役に立つの?」と思うようなことでも、診断の手がかりになることがあります。
躊躇せず、気になることはすべて伝えるようにしましょう。
3 坐骨神経痛の多様な原因を解説

坐骨神経痛は、坐骨神経という神経(神経の束)が圧迫されることが原因で起こります。
この神経を圧迫する原因には様々なものがあります。
例えば、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などが代表的な原因疾患です。
●【坐骨神経痛の原因要素】
坐骨神経痛の原因は人それぞれ異なりますが、いくつかの要素が関与しています。
具体的には、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症に加えて、腰椎すべり症、腰椎分離症、梨状筋症候群などが考えられます。
これらの疾患が坐骨神経に触れたり影響を与えることで、下肢や腰に痛み、違和感、感覚の低下などの症状が現れます。
●【坐骨神経痛の原因になりえる可能性】
坐骨神経痛の原因は一つだけではなく、複数の要素が影響していることが多いです。
例えば、姿勢の悪さや長時間の座り仕事、運動不足、肥満、加齢による骨や筋肉の変性、外傷なども坐骨神経痛のリスクを高めます。
また、遺伝的な要因やストレス、喫煙も関与する可能性があります。
さらに、女性の場合、妊娠や出産による骨盤の変化も坐骨神経痛の原因となりえます。
したがって、坐骨神経痛を予防・改善するためには、これらの原因要素を総合的に考慮し、生活習慣の改善や適切な治療を行うことが重要です。
日常生活では、正しい姿勢を保ち、適度な運動を心がけ、健康的な体重を維持することが坐骨神経痛の予防に役立ちます。
坐骨神経痛の原因は人それぞれ違うので、一つだけの原因ではない可能性もあって、複数の要素が影響している事が多いとも言えるでしょう。
参考になればうれしいです。
4 坐骨神経痛の概要とその状態

「坐骨神経痛」は病名ではなく、症状を表す言葉です。
腰痛、頭痛、腹痛なども同様に症状名であり、診断名としては使用されません。
カルテに診断名を記入する場所がありますが、通常、ここに「○○痛」という症状名は入りません。
ただし、現実には原因が確定できない場合、便宜上、症状名が書かれることもあります。
坐骨神経痛の原因を短時間で特定するのは困難な場合もあり、このような表現を使わざるを得ないこともあります。
参考までに、「○○疑い」という診断名も正式なものではなく、診断が確定できないときに便宜上使用される表現です。
「坐骨神経痛」と呼ばれる理由
坐骨神経痛という名前は、坐骨神経に何らかの障害(圧迫など)が生じ、その坐骨神経が支配する皮膚などの領域に痛みが放散する(放散痛)ことから由来しています。
坐骨神経の束の中にある感覚神経(痛覚)が刺激を受けると、その刺激は脳へ伝わり、痛みとして感じられます。
つまり、痛みを感じるのは神経自体ではなく、脳なのです。
このような仕組みを理解することで、症状の把握や治療方法の選択に役立ちます。
また、日常生活での注意点や予防策を講じる際にも重要な知識となります。
坐骨神経痛の坐骨神経って何?どこにあるの?
坐骨神経痛とは、坐骨神経に何らかの障害(圧迫など)が生じ、その結果として坐骨神経が支配する皮膚などの領域に痛みが放散する(放散痛)状態を指します。
坐骨神経の束の中にある感覚神経(痛覚)が刺激を受けると、その刺激は脳へ伝わり、痛みとして感じられます。
つまり、痛みを感じるのは神経自体ではなく、脳なのです。
この仕組みを理解することで、症状の把握や治療方法の選択に役立ちます。
脊柱(背骨)の中には脊髄(神経の束)が通っています。
脊髄から枝分かれした神経は脊柱を構成する椎骨の間から出て、末梢神経として人体の各部位へ伸びていきます。
腰椎の下部(L4, L5)から仙骨の上部(S1〜S3)までの神経が束となったものが坐骨神経です。
坐骨神経は梨状筋の前を通り、骨盤から出て太ももの裏側を通りながら枝分かれして足の方へ進んでいきます。
このため、坐骨神経という名称から、途中で枝分かれした各神経の名称へ変わっていきます。
坐骨神経痛は、神経が圧迫されることによって引き起こされるため、適切な治療や予防策を講じることで、症状を軽減したり予防したりすることが可能です。

脊椎 イメージイラスト

股関節の深層筋イラスト・後ろから見た図
5 坐骨神経痛になりやすい人の特徴

坐骨神経痛になりやすい人の特徴がいくつかありますのでご紹介します。
この特徴に当てはまっていても発症しない場合があることは勿論ですが、たくさん当てはまる人は注意しましょう。
- 姿勢が悪い(背中が丸くなっているなど)
- 長時間腰かけることが多い(デスクワーク、長距離運転)
- 中腰での作業が多い
- 重いものを持ち上げる(運ぶ)ことが多い
- 親、兄弟に坐骨神経痛(腰椎椎間板ヘルニアなど)の人がいる
- 腰に違和感があったり痛みを感じたりすることがある
- 激しいスポーツをしている、またはしていた
- 腰椎分離症など、腰部疾患の診断を受けたことがある
参考までに、性格の面では、
- 強引なタイプ
- せっかちなタイプ
- 他人に仕事を頼めないタイプ
上記の人は、人に頼らず、自分で無理してでもやってしまうことが多いので、腰を痛めやすいです。
不利な性格となります(筆者自身)。
以上、主な特徴をあげてみました。
若い方で発症する場合、腰への大きなストレス(重いものを扱う、介護業務など)が原因となることが多いです。
また、残念ながら遺伝的な影響も少なからずあります。
椎間板に障害が出やすい遺伝子を持っている場合、発症しやすくなります。
6 まとめ:坐骨神経痛の症状を理解し、対策と治療を進めよう
今回は坐骨神経痛の原因と対策についてお伝えしました。
坐骨神経痛は痛みだけでなく、進行すると下肢の麻痺やそれに伴う歩行障害、また膀胱直腸障害など、重度の症状を起こすことがあります。
日ごろから、対策をして予防をしておきましょう。
腰に痛みなどを感じている方は、坐骨神経痛の予備軍である可能性があります。
しびれや感覚の鈍いところはないか、つま先の上がり方が悪くなっていないか(筋力低下、麻痺)など注意しておいてください。
もし神経の症状が出たときは、早めに医師の診察を受けていただき、早めの対策をしていただけたらと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
皆様のご健康をお祈りいたします。
執筆者:mamotteライター 理学療法士 イワモト
追記・編集:mamotte運営管理者 理学療法士 平林

※ 編集を終えて:最後に ※
坐骨神経痛と診断されると不安になってしまいますよね。
しびれや痛みで思うようにいかない事など沢山あるでしょう。
でも、坐骨神経痛を治す事はできます。
何故、坐骨神経痛になってしまったのか?
という原因を突き止める必要があるでしょう。
また、本当に坐骨神経痛なのか?と疑わなくてはいけません。
坐骨神経痛と医者から言われても、
【坐骨神経痛と違った症状が体に表れている】
という方も少なくありません。
なので、坐骨神経痛と診断されても、ある意味一つの参考程度にするのがいいでしょう。
そして、
【今、感じている症状を治す為にはどうすればいいのか?】
ということだけを考えて、治療に臨むのがいいと思います。
診断名に惑わされてしまうと、その診断が違っていた場合に、治療も間違ってしまう。
といったリスクが伴います。
なので、信じる部分は、自分の症状に素直になる事だと思うのです。
- 坐骨神経痛だから、この治療
- 椎間板ヘルニアだから、この治療
- 脊柱管狭窄症だから、この治療
などと、型にはめた思考で治療を行わない事がなによりも大切だと思うわけです。
是非、参考にしてほしいなと思います。
運営管理者 理学療法士 平林
坐骨神経痛にクッションは使うべき!その理由を理学療法士が紹介
この記事を読む事で、
理解できる内容
- クッションの効果:坐骨神経痛においてクッションがどのように役立つかについての説明が含まれるでしょう。これには、座位時の圧力分散や姿勢のサポートなどの効果が考えられます。
- 推奨されるクッションの種類:理学療法士が推奨するクッションの種類や特性についての情報が提供される可能性があります。これには、形状、材質、サイズなどが含まれるかもしれません。
- 使用方法と注意点:クッションの最適な使用方法と、使い方における注意点についてのアドバイスが含まれることが期待されます。
理解できるメリット
- 痛みの軽減:適切なクッションを使用することで、座位時の坐骨神経への圧力が軽減され、痛みの緩和が期待できます。
- 姿勢の改善:クッションが正しい座位姿勢をサポートすることにより、長時間の座り仕事などでも姿勢が保たれ、坐骨神経痛の予防に役立ちます。
- 日常生活の質の向上:痛みが軽減され、姿勢が改善されることで、日常生活の質が向上し、仕事や家庭での活動が快適になる可能性があります。
といったメリットがあります。
是非、参考にしてください
最新記事 by mamotte (全て見る)
- 体重が引き起こす腰の痛み:肥満が腰痛に及ぼす具体的な影響 - 2024年5月28日
- 腰痛の背後に潜む?専門家が指摘する可能性のある12の病気 - 2022年5月4日
- 腰痛対策!医者に行く前に試すべき生活習慣の見直し方 - 2022年2月17日
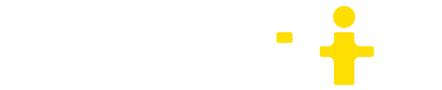














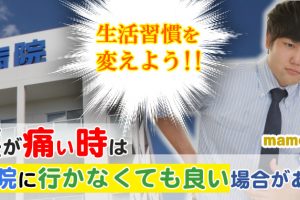




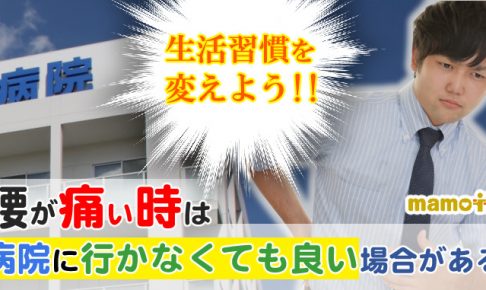



mamotteライターで理学療法士のイワモトです。
今回は【坐骨神経痛の原因】をテーマに記事にしました。
坐骨神経痛の原因はなにか?
そして、どのような思考で良くなるのか?
坐骨神経痛はよく聞くけど、何が原因でどうしたらよくなるのか?
といった疑問に対して、答えられるような記事にしました。
この記事を読めば
◎ 坐骨神経痛の原因を理解できて、治す為に必要な思考についても知れる。そして、実際に坐骨神経痛を治すために近づける
といった点があります。
最後まで読んでほしいなと思います。
では、よろしくお願いいたします。