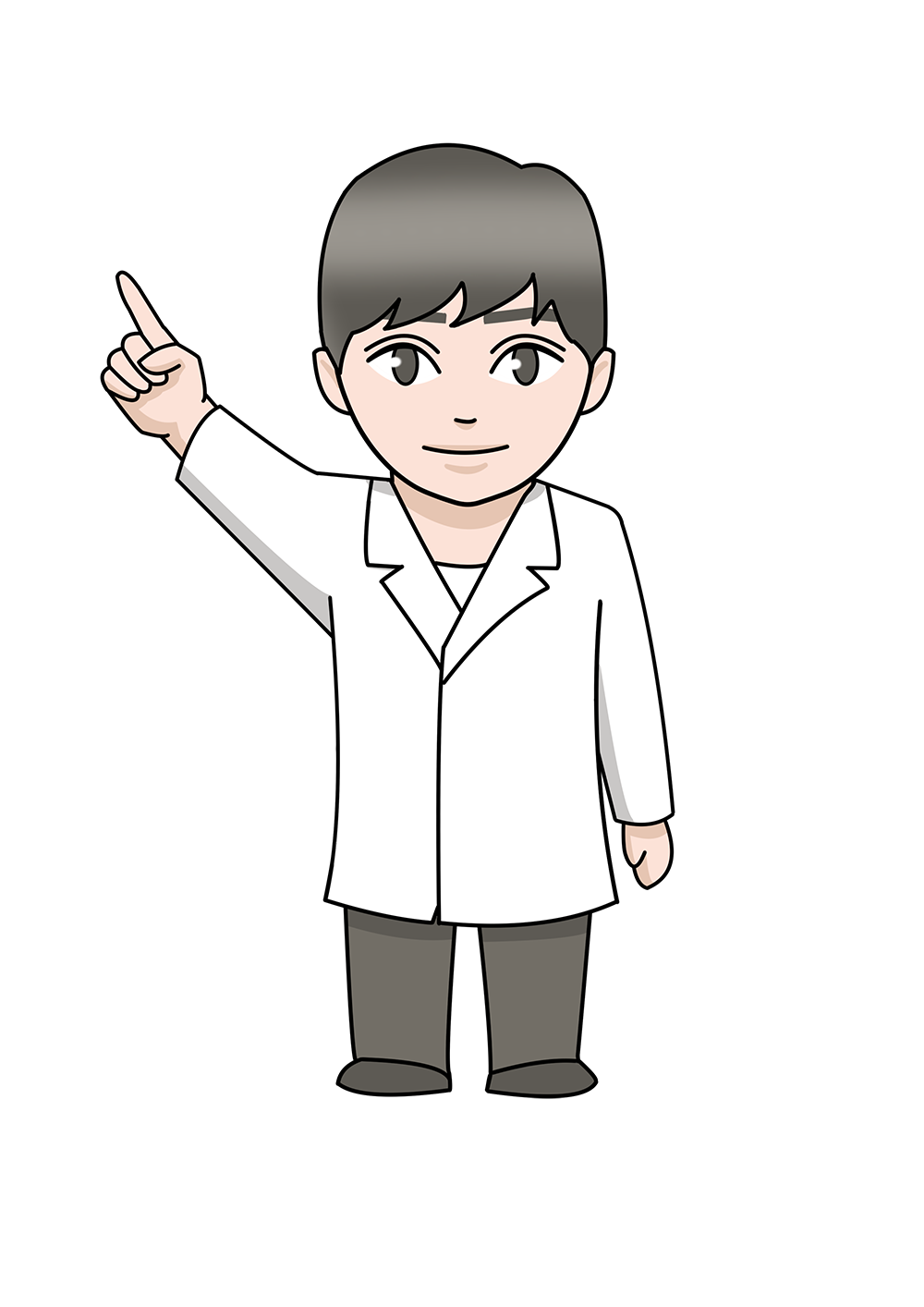

私達は国家資格を取得しており、実際の現場で学んできています。
ですので、信憑性や信頼性は間違いありません。
共感する部分は、共感して頂き、納得できる内容は納得して欲しいと思います。
で、一番伝えたい事は、【この記事の内容が絶対正しい!!】とは思わないでください。
という事です。
記事の内容は自信を持って提供していますが、医療の世界は個人的な意見や見解もあるので、解釈は人それぞれです。
ですので、一つの理学療法士の考えである。と捉えてください。
この記事があなたの役に立てばうれしいです。
では、宜しくお願いいたします。
1 椎間板ヘルニアの症状について

では、椎間板ヘルニアの症状について話していきますね。
腰に多く起こる椎間板ヘルニアは、その発生する場所によって症状が違ってきます。
よく、「L4,5のヘルニア」などと表現されており、この「L4,5」というのは、発症部位を示しています。
Lは腰椎の事を指しており、腰部分の事をいいます。
腰の骨は1~5個あると言われており、L4.5は腰の下の部分を表している事になります。
椎間板ヘルニアは、痛み(放散痛)やしびれなどの症状が多いです。
腰の場合、ヘルニアが進行すると、足の筋力が低下して、つまずいたり、足を持ち上げにくいなどの歩行障害を起こしたり、日常生活がしづらくなる事が多いです。
さらに、進むと排尿障害などの症状が出現する場合もあります。
ここまでくると腰の椎間板ヘルニアとしてはちょっと危ない感じです。
排尿障害とは、尿意を感じず無意識に出てしまったり、ちょっとでも我慢できなくなってしまったりする事です。
排泄のコントロールができないと、生命の危険にまで及ぼすので、早期な治療を考える段階ともいえるでしょう。
また、首のヘルニアの場合は、首から手にかけての痛みやしびれ、違和感など。
上肢に影響した症状が起きます。
力が入らなかったりする事もあるので、実際の症状は個人によって、かわってきます。
このように、ヘルニアは痛みやしびれを主にした症状を感じて、日常生活に支障を与える事があるのです。
参考程度に覚えてほしいなと思います。
2 ヘルニアの部位によって症状が変わる

ヘルニアはどこに起きるのか?
起きる部位・場所によって、症状も若干変わってきます。
どういう事かというと。
首の骨は1~7つ、腰は1~5つあると言われています。
首なら1~7つの間、腰なら1~5つの間。
このどこにヘルニアが起きるか?によって、症状が若干違ってくるよ。
というお話です。
神経には、下記のような感じで支配されている箇所が違います。
下記は腰のイラストですが。

神経支配領域のイラスト
このように、どこにヘルニアが起きるのか?によって、足に生じる症状も若干違ってくるのです。
とはいっても、ヘルニアになってしまったら、足の全体に感じる人もいるので同じ部位でも症状の出方が人によって違う(感じ方が違う)場合も多々ある。
という認識をもっておくといいかと思います。
では、簡単に説明していきます。
腰のヘルニアのみになりますが、参考にしてください。
第1と第2の椎間板ヘルニア L1とL2
腰周囲への痛み、しびれを生じます。
股関節を曲げる(立った姿勢で、太ももを上げる)筋力が弱くなることがあります。
第2と第3の椎間板ヘルニア L2とL3
腰の下周囲からそけい部(股関節の内側)、太ももの内側あたりに痛みやしびれが生じます。
股関節を曲げる筋(腸腰筋)や膝を伸ばす筋(大腿四頭筋)の筋力低下を起こすことがあります。
片足立ちで膝の屈伸ができない、階段を下りる時に膝がカクッと折れるような感じがするなどがあります。
第3と第4の椎間板ヘルニア L3とL4
太ももの前側から膝の内側に痛みやしびれを生じます。
膝を伸ばす筋や股関節の内転筋(股を閉じる筋)に筋力低下を生じることがあります。
第4と第5の椎間板ヘルニア L4とL5
発症が最も多い場所です。
おしりから太ももの外側、すね、親指の先あたりまで広い範囲で痛みが走ったり、しびれを生じたりします。
つま先を上げる筋や股関節を外転筋(足を外に開く筋)などに筋力低下を起こすことがあります。
スリッパが脱げやすくなったり、つまずきやすくなったりします。
医師の診察の時に母趾(ぼし・足の親指)を反らす筋力検査(長母趾伸筋)をするのはこのためです。
第5と仙骨(尾てい骨)の椎間板ヘルニア L5と仙骨
おしりから太ももの裏を通って、ふくらはぎ、踵(かかと)、足底(足の裏)、小指にかけて痛みやしびれを生じます。
つま先を下げる筋(ふくらはぎの筋)、膝を曲げる筋(太ももの裏側の筋)などの筋力低下を起こすことがあります。
つま先立ちが難しくなります。
以上、参考にしてください。
3 椎間板ヘルニアが進行するとどうなるの?

ヘルニアの軽い段階では、症状を感じないかまたは、わずかなしびれ感、痛みの症状が主です。
進行に伴い、しびれや痛みが徐々に強くなっていきます。
さらに進行すると、痛みやしびれが激しくなるため、歩くのが辛いなど日常生活に支障をきたすようにもなります。
また、痛みやしびれがひどくならなくても、気付かない間にヘルニアが進行しているという場合もあります。
なので、神経への圧迫が長期におよぶ場合には筋力低下(麻痺)を起こすこともあるでしょう。
で、排尿・排便にかかわる神経を圧迫すると、尿や便が出にくいなどの障害を生じる事少なくありません。
このような症状が出てきた場合は重度と考えてよいでしょう。
進行のしかたと症状の出方は、個人によって、様々です。
強い痛みやしびれがなく、麻痺が進行しているといった可能性も人によってはあります。
ですので、必ずこのような症状になる!!
という断言は難しいのですが、ある程度のパターンは予想も想像できるので、参考にしてください。
で、何よりも、進行させない事が大事なので、対処や解決策・治療に取り組むのがいいでしょう。
4 椎間板ヘルニアにならない為にするべき事

椎間板ヘルニアは一度なってしまうと、再発を繰り返しやすいし、場合によっては手術が必要となります。
なので、当たり前の事ですが、できるだけ椎間板ヘルニアを起こさないように予防をこころがけるのが必要です。
すでに経験した方は、再発予防に努めましょう。
100%予防する方法はありませんが、心掛けることによって発症の危険を下げることは確実にできます。
20歳を過ぎると椎間板は老化を始めるとも言われています。
老化すると、弱くなった部分から椎間板の中にある髄核(ずいかく)が飛び出しやすくなりますので、できるだけ椎間板に無理な力がかからないようにするのが基本です。
では、これより具体的にするべきことを挙げてみます。
例1
物を持ち上げる時は必ず膝を曲げ、物と体が離れないように近づいてから持ち上げるようにします。
力の強い方は無理な姿勢でも重い物を持ち上げることができてしまいますので、力が弱い方よりもさらに注意が必要になります。

●膝を落として、体全体で持ち上げます
例2
ごみを拾うなど、軽い物を取るときも徹底して行いましょう。
多くの方が上半身だけを前に倒して物を拾っていますが、この動作は椎間板に大きな力をかけます
例3
中腰での作業は、できるだけ上半身が前に倒れすぎないように注意します。
普段から動作と腰への負担を考えながら生活をしてみてください。
この動作は腰に負担がかかるということに気付いたら、その動作をひかえたり、動作の仕方を変えるようにしましょう。
また、姿勢の改善も大切です。
◎背中を丸めた姿勢で長時間腰かけていたり、床に足をのばして座っていたりするのは控えましょう。
できるだけ背中が丸くならない良い姿勢を心掛け、途中で体操をしたり、姿勢を変えたりすつといいです。
◎長時間の車の運転も腰に負担がかかりますので、定期的に体操をしたり、腰椎をサポートするクッションを用いたりするなどの工夫もすると良いでしょう。
このように、普段の姿勢や日常生活動作を意識して癖づける事がなによりも大切になります。
◎細かい事では、片手で荷物をもって長時間歩かないようにする。
スーパーでの買い物はかごを持たず、カートを使う。
買い物袋は2つに分けて両手均等に持つ。
重いごみ出しはキャリーカートを使う
なども対策としてよいでしょう。
この程度なら大丈夫と少し無理してしまうようなところを変えるのがポイントかなと思います。
で、別問題としたら、重労働(重い物を運ぶ、介護など)は発症の危険が高くなります。
仕事の影響が大きく、再発を繰り返している場合は、まず、対策を行う事です。
腰が痛くならないようにする為の方法を行いましょう。
それでも、腰痛が変わらない場合は、部署の異動などを願うのもありかもしれません。
しかし、正しい対処を行えば、どんな重労働でも対策は可能です。
適切な対応策、方法を身に着ける事がいいでしょう。
5 手術よりも、まずは、運動などで対処してみよう

では、実際の体験談と治療談について話していきますね。
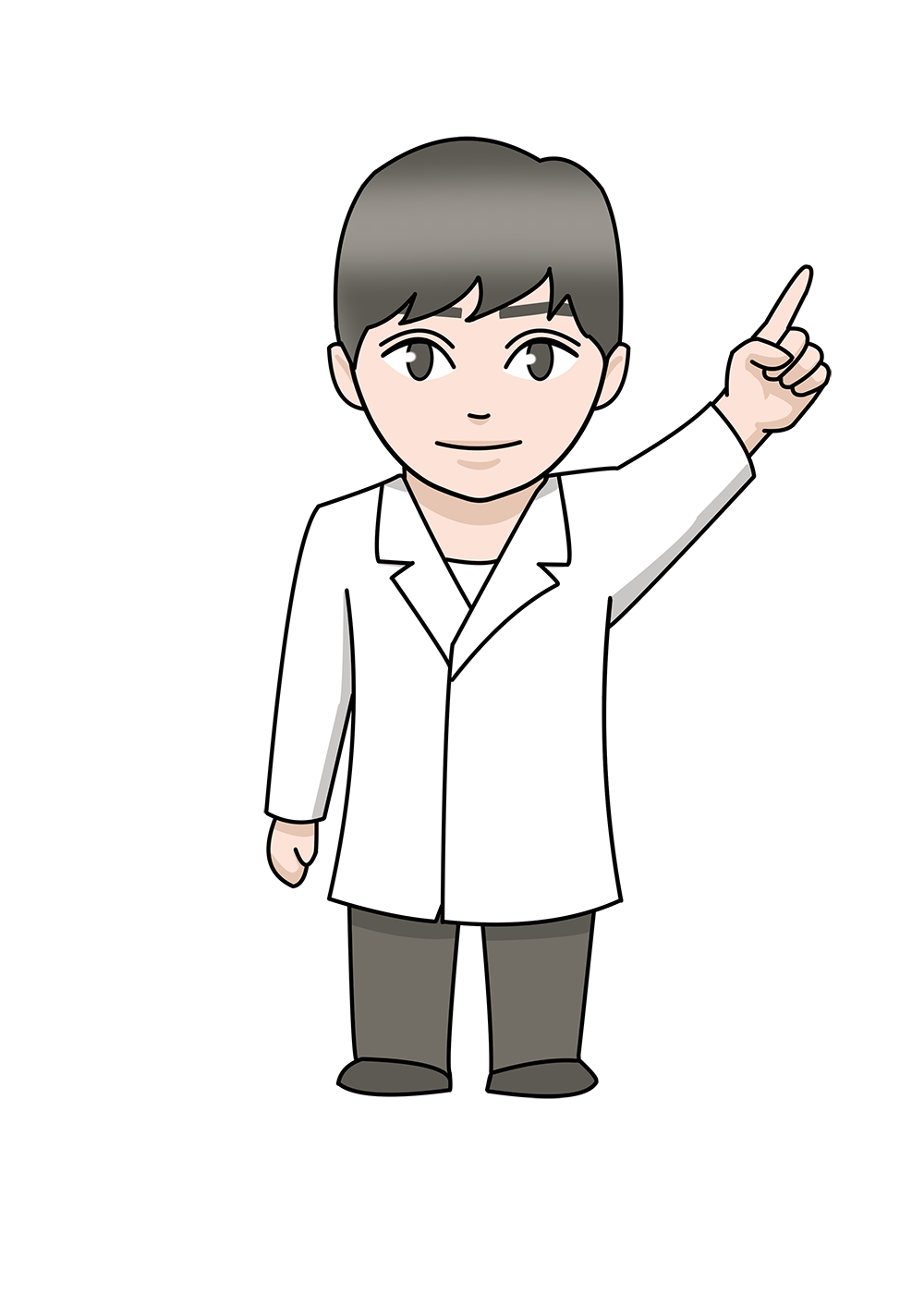
椎間板ヘルニアの患者さんと接する機会は多くありましたが、仕事柄、職員のヘルニアも多かったです。
リハビリの訓練や介護時の移乗介助は人ひとり抱えるため、腰には負担がかかります。
抱える動作がヘルニアの原因となるのは間違いないようです。
手術の効果については、身近にも家族を含め数人、手術を受けた方を知っていますが、術後の経過は良好でかなり良くなっています。
手術と言えば、家族がヘルニアの手術を受ける時に医師から説明を受けたのですが、「手術しなくても治るのに(軽い例)、日本人は我慢しないですぐに手術をしたがる」という話を聞きました。
日本は保険の制度上、手術を受けやすいし入院もゆっくりできますから(最近ちょっと短くなってきたけど)、それだけ恵まれていると思います。
ヘルニアは自然にもとに戻ったり、消失したりして治ることもありますけど、神経症状が強い場合は早めの対処がよいと思います。
良い医師と巡り合うことも重要なポイントです。
麻痺が進行しているのに筋力検査もしておらず、見逃していた例を知っています。
私も時々、足のしびれを感じながら生活しています。
頑張ってほしいなあと思います
6 まとめ:椎間板ヘルニアの症状を知って、予防・改善を目指そう
椎間板ヘルニアは発症する部位によって症状が異なります。
また、同じ部位でも症状の出方に違いがある場合もあります。
腰のヘルニアは腰と下肢に痛みやしびれを起こしやすい病態です。
足にしびれなど、普段と違った症状が出る場合は早めに受診してみましょう。
首のヘルニアは、首、肩、手に痛みやしびれ、違和感などを生じます。
少しでも感じる事があれば受診しましょう。
で、何よりも、ヘルニアを起こさないように予防するのが大切です。
普段の生活から腰や首への負担が強くならないように配慮していきましょう。
椎間板ヘルニアは【誰にでも発症する可能性】があります。
でも、予防・対策・改善させる事も不可能ではありません。
治る人もいるし、症状が軽減する人も沢山います。
絶対に治らない。
という訳ではないので、不安にならないでいいと思います。
重度な椎間板ヘルニアでも体操や姿勢の指導だけで、改善していった事例も少なくありません。
必ずといっていいくらい、対処方法はあるので、諦めず、改善・回復を目指していければいいのかなと思います。
という事で、今回の話があなたの力になれたらうれしく思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
執筆:mamotteライター 理学療法士 イワモト
追記・編集:運営者 理学療法士 平林

椎間板ヘルニアって診断されると怖いですよね・・・
痛みやしびれが治らないんじゃないかと・・・不安になるし、怖くなるでしょう。
手術するしか治療方法がない。
と思い込んでいる方もいると思います。
しかし、実際には手術をしなくても体操やストレッチだけで治る可能性も多いにあります。
これを知っていてもらいたいなぁという思いが、僕にはあります。
手術は、最後の最後の最後の最後の最後の手段
こんな感じで、手術は捉えてほしいなぁというのが個人的な思いです。
じゃあ、手術しない方法で治るのか?、治せるのか?
と思うとおもいますが。
実際には手術をしなくても、【治る可能性はゼロではないし、症状が軽減する可能性もある】(絶対ではありませんが)。
つまり、手術しなくても、症状を緩和、和らげる、うまくハマれば、改善する。
という人も少なくない。という事です。(実際に僕も治療している中で感じています。)
是非、頭の片隅においてほしいと思います。
今回の話が少しでも役立てばうれしいです。
本日も最後までありがとうございました。
椎間板ヘルニアの4つの主な症状について紹介されています。
また、手術をする方法、しない方法があって。
一体、どれが適切な治療であるのか?についても言及しています。
椎間板ヘルニアの症状を軽減、改善方向に持っていくためにはどのような支援が必要でしょうか。
これからも思考錯誤して状態が落ち着けばよいと思います。
最新記事 by mamotte (全て見る)
- 体重が引き起こす腰の痛み:肥満が腰痛に及ぼす具体的な影響 - 2024年5月28日
- 腰痛の背後に潜む?専門家が指摘する可能性のある12の病気 - 2022年5月4日
- 腰痛対策!医者に行く前に試すべき生活習慣の見直し方 - 2022年2月17日
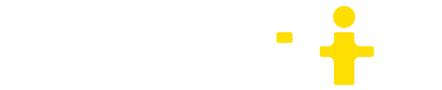





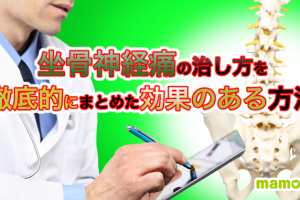








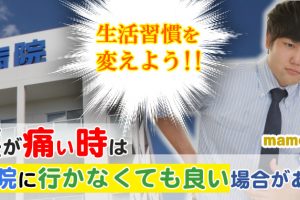




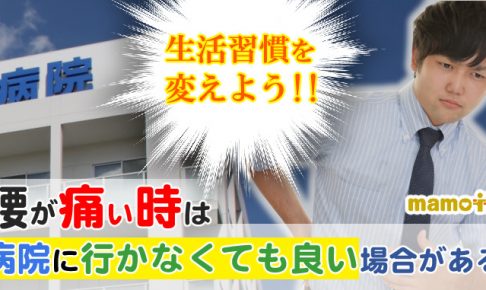



mamotteライターで理学療法士のイワモトです。
ヘルニアと聞くと、【なんか怖いな・・・】みたいな印象ありませんか?
よく聞く言葉としては、鼠経(そけい)ヘルニア、椎間板ヘルニアが代表的なものでしょう。
で、椎間板ヘルニアは首と腰に発症しやすくて、だれにでも起きる可能性があります。
そこで今回は、【椎間板ヘルニアの症状を解剖する】といったテーマで記事にしました。
この記事を読めば、
といった2点が得られます
是非、最後まで読んで参考になればうれしいです。